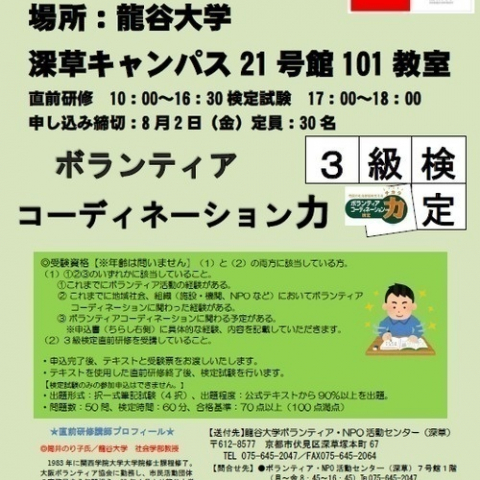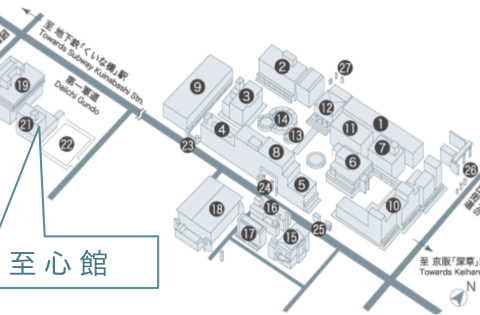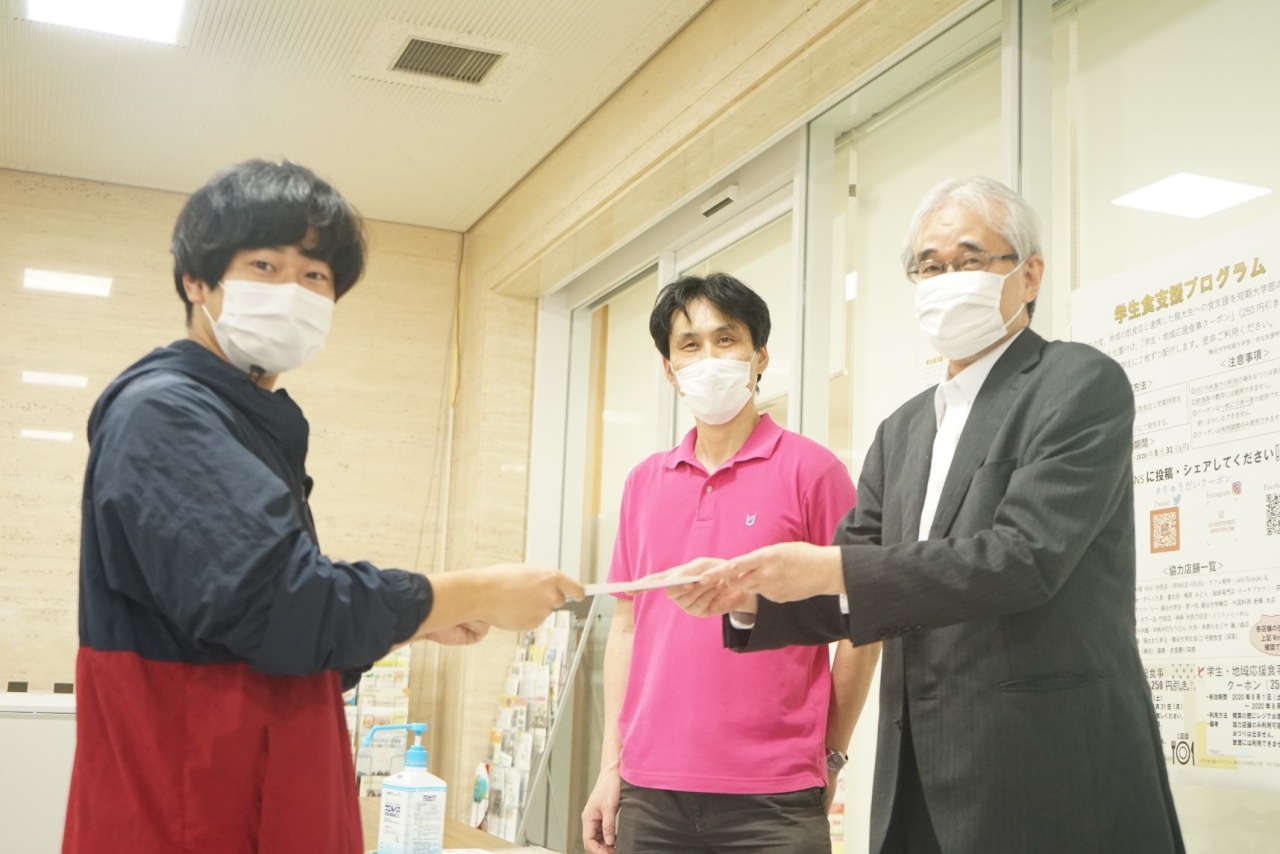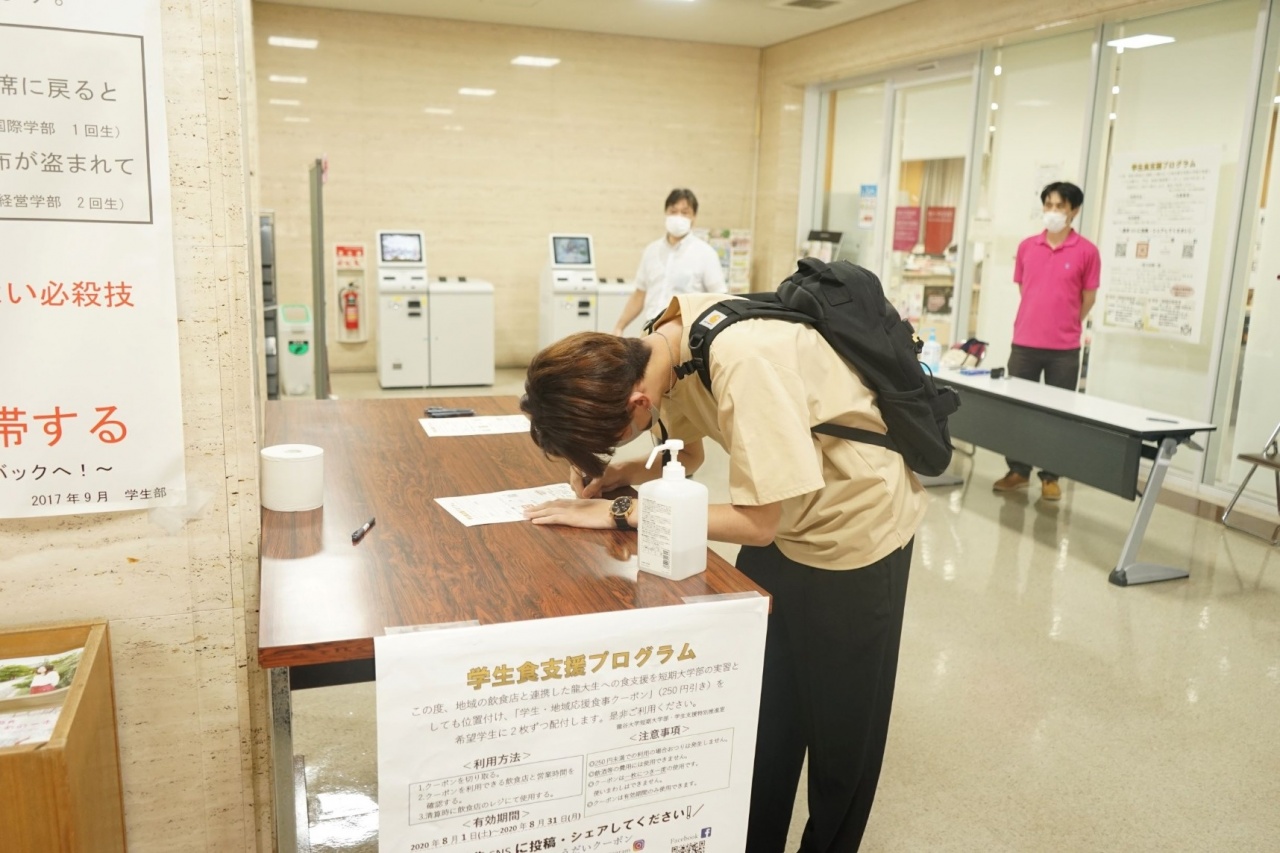オンラインオープンキャンパスでの文学部イベントについて【文学部】
今週末の8月1日、2日、オンラインでのオープンキャンパスを開催します。
教職員・在学生による各学部イベント・模擬授業体験・交流会や入試説明・キャンパスオンラインツアーなど、本学の魅力がつまった2日間です。
また、スペシャルゲストを多数迎えて、本学をさまざまな角度からお楽しみいただける企画もお届けします。
新型コロナウイルス感染拡大に伴い高校生との接点づくりが難しい中、大学に興味を持ってもらうきっかけとして、学びの魅力をお伝えする
コンテンツだけでなく、受験生応援企画やスポーツ、音楽、グルメなど多彩な切り口で、お楽しみいただけるような、特別な2日間をお送りします。
ぜひご視聴ください!
▼詳細は特設サイトにてご覧ください▼
URL オンラインオープンキャンパス
▼文学部イベント 是非ご覧ください!▼
★ 8月1日(土) <自由にご視聴ください>
12:00~12:30 全体説明会(安藤文学部長)
15:00~15:30 文学部コモンズカフェ(日本語日本文学科 高木彬先生)
「文学と空間」
15:30~16:00 共通セミナー(「龍大文学部とは?」)(内田准心先生)
11:00~16:00 個別相談(絶賛受付中先着20名)
★ 8月2日(日) <自由にご視聴ください>
12:00~12:30 全体説明会(安藤文学学部長)
15:00~15:30 文学部コモンズカフェ(臨床心理学科 伊東秀章先生)
「臨床心理学科の研究紹介」
11:00~16:00 個別相談 <絶賛受付中先着20名>
URL 8月1日(土)オンラインイベントプログラム
URL 8月2日(日)オンラインイベントプログラム
URL 8月22日(土)オンラインイベントプログラム
URL 8月23日(日)オンラインイベントプログラム