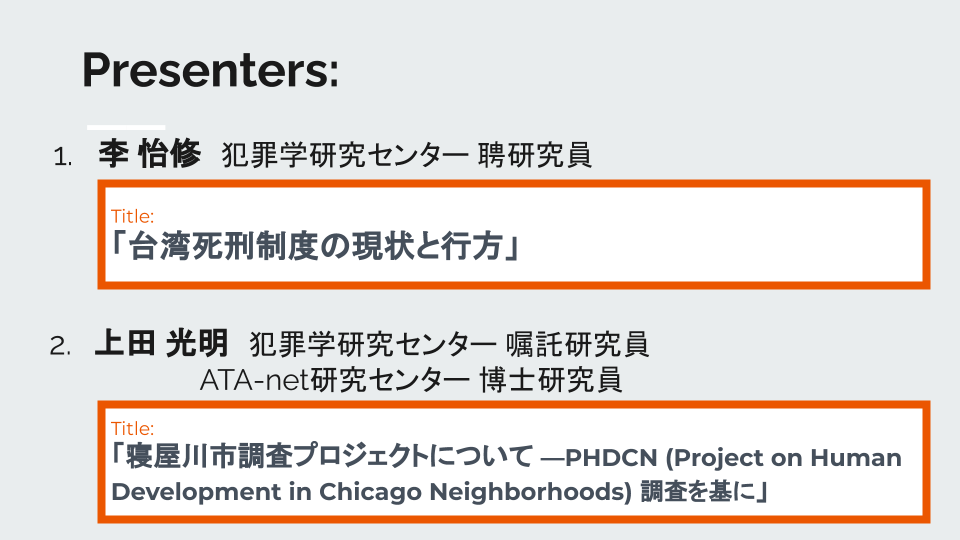2020年(令和2年)7月豪雨について Ver.2(一部情報更新)
この度の2020年7月豪雨で被害に遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
熊本県南部や鹿児島県北部・宮崎県において7月3日から激しい雨が降り続き、熊本県、鹿児島県では大雨特別警報が出されました。この関係で球磨川(くまがわ)をはじめとした河川の氾濫、また、各地で土砂災害が発生し、その後も九州全域、日本各地に被災範囲が広がっています。
ボランティア・NPO活動センターでは、この災害に関しての情報収集を行っているところです。被災された地域への災害ボランティアなどの支援活動に参加したいと考えている学生や教職員の皆さんもおられるかと思います。困難な状況にある人たちのことに想いを巡らせること、「何か手助けをしたい」と考え、行動しようとすることは、とても大切なことです。しかし、行動の仕方によっては、現地の方々に負荷をかけてしまう場合があります。特に被災直後は、命を守るための活動が最優先です。
豪雨被害にあった各地域では、災害ボランティアセンター立ち上げのための情報収集が始まっています。一部、災害支援のスキルをもったNPOが現地入りして活動を展開し始めたところもありますが、現在は、被災地域での住民や知人の助け合いによる作業が中心です。特に、今回の災害では、浸水被害に加え、避難生活による新型コロナウイルス感染拡大も心配されており、感染拡大防止という意味では被災地外からの災害ボランティアによる支援も慎重な判断が求められ、災害ボランティアセンターの設置・運営等については、非常に難しい判断が必要です。 ボランティアの受け入れ準備が整えば、まずは、県内で募集が始まり、次に県外の人の受けれとなるでしょう。県外の人が被災地域での活動が行えるようになるまでには時間がかかるかもしれません。被災地での活動については、(専門技能や活動スキルがある人以外は)被災地域からボランティア募集に関する発信があるまで、ボランティア活動を目的として被災地に向かうことは控えるようお願いします。
現地に行けなくても、「募金活動」や「必要な支援物資送る」(物資を送る際は、様々な配慮が必要です。送り方によっては、かえって被災地に負荷をかける場合がありますのでご注意ください)など、様々な応援の方法があります。センターでは、そういった情報も収集しておりますので、何かしたいと考えている学生、教職員は、ぜひ、センターまでご相談ください。
状況は刻々と変化しています。今後の情報を注視しておいてください。
****************************************************************
最後に、現在、被災地域やその付近に居住している学生で、ボランティア活動を考えている学生は、安全と下記の点に留意してボランティア活動を行ってください。
- 被災地で安全に活動するためには必要な準備があります。下記の団体の「災害ボラの予備知識」(認定特定非営利活動法人レスキューストックヤード)を参照して、十分に準備を行ってください。※コロナ感染予防対策だけではなく、熱中症対策なども十分に行い、こまめに休憩をとりながら安全に活動することに留意お願いします。
- ボランティア保険の加入は、最寄りの社会福祉協議会で加入出来ますので、近隣で活動する際でも加入することをお勧めします。近い内に即日発行できるようになるかと思いますが、現状(7月6日現在)は加入翌日からの発行になりますので、注意してください。水害には天災プランの加入は必要ありません。通常プランに加入してください。※2020年4月以降にボランティア保険に加入された方は、再度加入する必要はありません。★一部被災地域に居住の方のみ、Webからの加入も可能になりました。注意事項を確認の上、加入手続きをしてください。
- 被災した地域の状況は刻々と変化しており、ボランティアの募集状況も変化しています。最新の情報は、全国社会福祉協議会・災害ボランティア情報等をWebで調べることが出来ます。参加する際には、必ず、最新の情報を調べてから参加するようにしましょう。
- 現在(7月14日現在)、岐阜県、長崎県、福岡県、熊本県、大分県内で災害ボランティアセンターが立ち上がっていますが、基本的には、県内に居住の方のボランティア募集になっています。混雑緩和のために事前予約が必要なところもあるので、必ず、活動しようと考えているボランティアセンターの最新情報を確認の上、活動に参加してください。