ブラウザからレイアウト自由自在
Layout Module
ここにメッセージを入れることができます。

政策実践・探求演習ⅠA ⅡA(海外)フィールドワーク実施【政策学部】
「政策実践・探求演習ⅠA ⅡA(海外)」(担当:金紅実 准教授・谷垣岳人...

新任教員の紹介 (10) (文学部真宗学科 内田准心 講師)【文学部】
2018年4月に文学部に新たに着任した教員を紹介します。 文学部真宗学科 ...

【報告】斯文会(文学部教授会)様より、「東日本大震災等復興支援募金」へのご寄付をいただきました。
斯文会(文学部教授会)様より、本学の教育研究等振興資金「東日本大震災...

センターでは、学生が何か新しいことを始めたいと感じる年度初めに、こ...

新たな水田農業の提案「水田転換畑」に関する記者レクチャーを行いました【農学部】
2018年6月5日(火)14:00~京都大学大学記者クラブにおいて、龍谷大学農...

2017年度からの新設科目である「法政アクティブリサーチ」の報告会と募...
龍谷大学親和会の「学業優秀者表彰制度」において、2018年度の「学部教育賞」に選出されたグループに対して、表彰式を行いました。
「学業優秀者表彰制度」は、学業において著しい成績・成果をおさめた個人・ゼミに対し、学生が意欲的に自らの目標に向かって自己研鑚することを奨励する表彰制度です。その中の「学部教育賞」は政策学部においては、各年度において政策学部の特性に合った活動で成果をあげた個人またはグループに対して表彰をすることとし、2018年度は、「阿部大輔ゼミナール」と「石原凌河ゼミナール」が選出されました。
「第9回アーバンデザイン甲子園」(2018年12月9日開催/主催・日本建築学会近畿支部都市計画部会)において、阿部ゼミの作品が、審査員特別賞を受賞しました。また、石原ゼミも入賞を受賞し高い評価を得ました。
また、石原ゼミは“You, Challenger” Project として1年間ゼミ活動について広報発信を積極的に行いました。
政策学部には地域や社会の課題解決のために活発に活動しているゼミやグループがたくさんあります。ゼミ受賞グループの今後の活躍に期待するとともに、他のグループも切磋琢磨しながら活動に取り組んでいただきたいと思います。
【本件のポイント】
・龍谷大学瀬田学舎の開学30周年、理工学部開設30周年を記念し、公開討論会を開催
・2020(令和2)年4月から新たに歩み始める龍谷大学先端理工学部に対し「地域と大学の共生のために先端理工学部ができること」をテーマにディスカッション
この度、龍谷大学瀬田学舎30周年記念事業のとして、『理工学部開設30周年記念公開討論会〜地域と大学の共生のために先端理工学部ができること〜』と題して公開討論会を開催します。
平成元年に開設し、令和元年で30周年を迎える理工学部は、2020(令和2)年4月に先端理工学部として新たな歩みを始めることとなり、現在、開設に向けての準備を進めています。
公開討論会では滋賀県商工観光労働部長の森中高史氏をはじめ、日本電産株式会社 精密小型モータ事業本部第4開発統括部長の櫻田国士氏、光泉中学・高等学校 進路指導部の三大寺光氏をお招きし、本学理工学部の松木平淳太学部長(先端理工学部長に就任予定)と「①先端理工学部の特徴、②社会からの希望・要請、③地域と大学の共生」について、企業・教育・行政の視点から、『時代とともに変化する社会から求められる人材』やSociety5.0、SDGsを意識できる人材等について、新たに生まれ変わる先端理工学部が社会に還元できることは何なのかを討論します。
「企業・教育・行政」のパネリストから、新たな歩みを始める先端理工学部に対して忌憚のない意見を頂戴し、『時代とともに変化する社会から求められる人材』を導き出し、先端理工学部のプレゼンス向上へと繋げたいと考えています。
1 開催日 2019年10月26日(土) 10時~11時30分
2 場所 龍谷大学瀬田キャンパス 8号館103教室
(大津市瀬田大江町横谷1-5)
3 テーマ 「地域と大学の共生のために先端理工学部ができること」
4 パネリスト
森中 高史 氏 滋賀県商工観光労働部長
櫻田 国士 氏 日本電産株式会社 精密小型モータ事業本部第4開発統括部長
(本学大学院理工学研究科物質化学専攻修了)
三大寺 光 氏 光泉中学・高等学校 進路指導部(元京都府立桂高校副校長)
松木平 淳太 本学理工学部長(先端理工学部長に就任予定)
(司会)富﨑 欣也 本学理工学部物質化学科教授
5 その他 申し込み不要。参加に制限はありません。
問い合わせ先 : 龍谷大学理工学部教務課 田畑 Tel 077-543-7730

本学文学部と熊本県・熊本県教育委員会主催の鞠智城シンポジウム「古代の山城と東北城柵」が10月6日(日)龍谷大学響都ホールで開催され、全国から225名の市民参加をいただきました。運営では、文化遺産学専攻1年生の協力を得て無事終了。有意義な歴史シンポジウムになりました。。
オープニングは、熊本県のPRキャラクター・くまモン、 鞠智城のゆるキャラ・ころう君も登場、和やかな雰囲気でスタート。龍谷大学学長、熊本県ご挨拶のち1本の報告、4本の講演、パネルデスカッションが行われ、白熱した議論が行われました。講師の先生方、熊本県の関係者の皆様、ありがとうございました。



文学部歴史学科文化遺産学専攻 國下多美樹教授
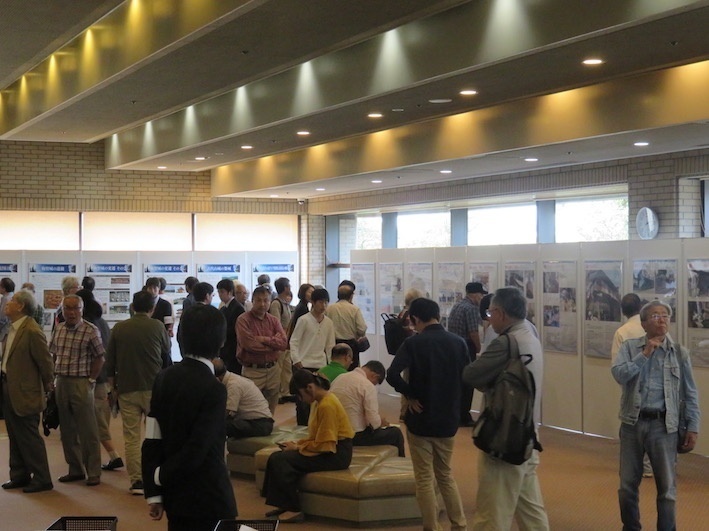
本学学生のベンチャーマインドの育成と大学発学生ベンチャーの発掘を目的に、2001(平成13)年度からビジネスプランコンテスト「プレゼン龍(ドラゴン)」を開催しています。
19回目の開催となる本年は、「プレゼン龍×SDGs」をテーマに掲げ、貧困や飢餓、健康、福祉、エネルギー、自然などに対して解決すべき社会課題を身近なところから考え、世界につながる社会課題解決のアイデアやビジネスプランを募集しています。
エントリーに先立ち、10月に事前学習として特別講演会&龍起業塾を開催しました。
事業概要:https://rec.seta.ryukoku.ac.jp/venture/presendragon/yoko.html
特別講演会&龍起業塾:https://rec.seta.ryukoku.ac.jp/venture/presendragon/lecture.html
【特別講演会①】 10月9日(水)16:45〜18:15
「~ケニア女子学生支援と日本人学生とのかかわりからみたSDGs~」
講師:shiho ミュージックアクティビスト(音楽活動家)
会場:深草キャンパス 和顔館地下1階 B104教室
【特別講演会②】 10月11日(金) 16:45〜18:15
「アイデアをカタチにして持続可能な社会を実現
~Makuake流クラウドファンディング活用術~」
講師:菊地凌輔(株式会社マクアケ 西日本事業部・関西支社社長)
会場:深草キャンパス 和顔館2階 202教室
<龍起業塾①>「アイデアの出し方」 講師:深尾昌峰 政策学部教授
【深草】10月1日(火) 16:45~18:15 会場:和顔館地下1階 B106教室
【瀬田】10月7日(月) 17:00~18:30 会場:REC小ホール
<龍起業塾②>「ビジネスプラン作成に必要な行動」 講師:秋庭太 経営学部准教授
【深草】10月3日(木) 16:45~18:15 会場:和顔館地下1階 B106教室
【瀬田】10月10日(木) 17:00~18:30 会場:REC101会議室