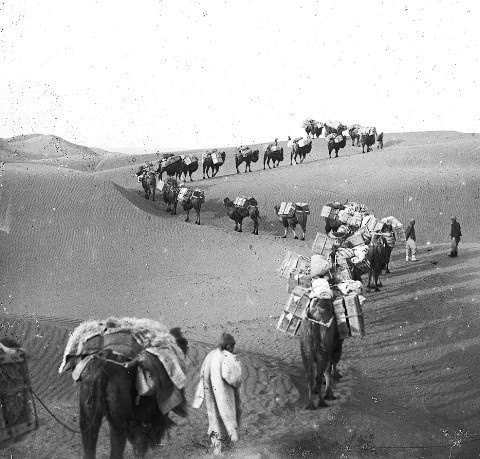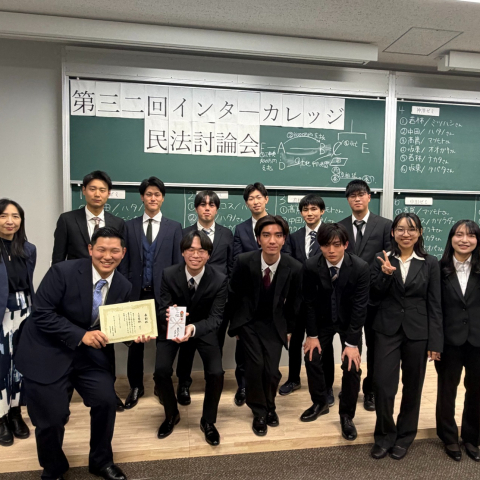入試部 冬期休業のおしらせ
入試部の冬期休業期間は、
年末12月27日(土)から年始1月5日(月)までとなっております。
入試部宛のメール等でのお問い合わせについては、
12月25日(木)以降にお問い合わせいただいた場合、
ご返答が年明け1月6日(火)以降になりますので、予めご了承願います。
一般選抜入試、共通テスト利用入試については、入学試験要項をまずはご確認ください。
・入学試験要項はコチラ
年末年始におけるインターネットからの入試要項等の資料発送スケジュールは以下のとおりです。
12月29日(月)までに申込みいただいた場合、翌日に発送いたします。
12月30日(火)~1月4日(日)の間にお申込みいただいた場合、1月5日(月)に発送いたします。
※12月中旬〜1月初旬までの期間は、各運送業者が大変混み合う時期となっております。
余裕を持って資料請求してください。
・資料請求はコチラ
0570-017887(ナビダイヤル)
受付時間:平日 9:00~17:00(本学休業日を除く)