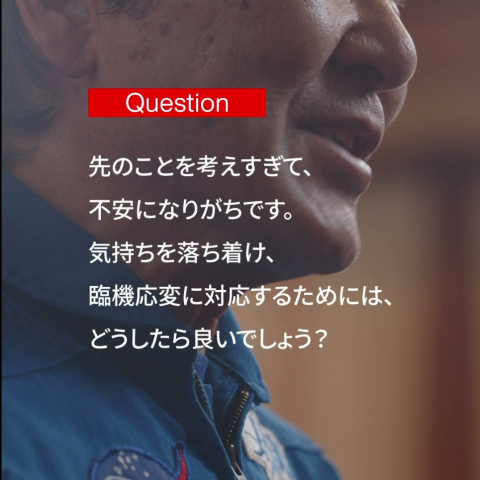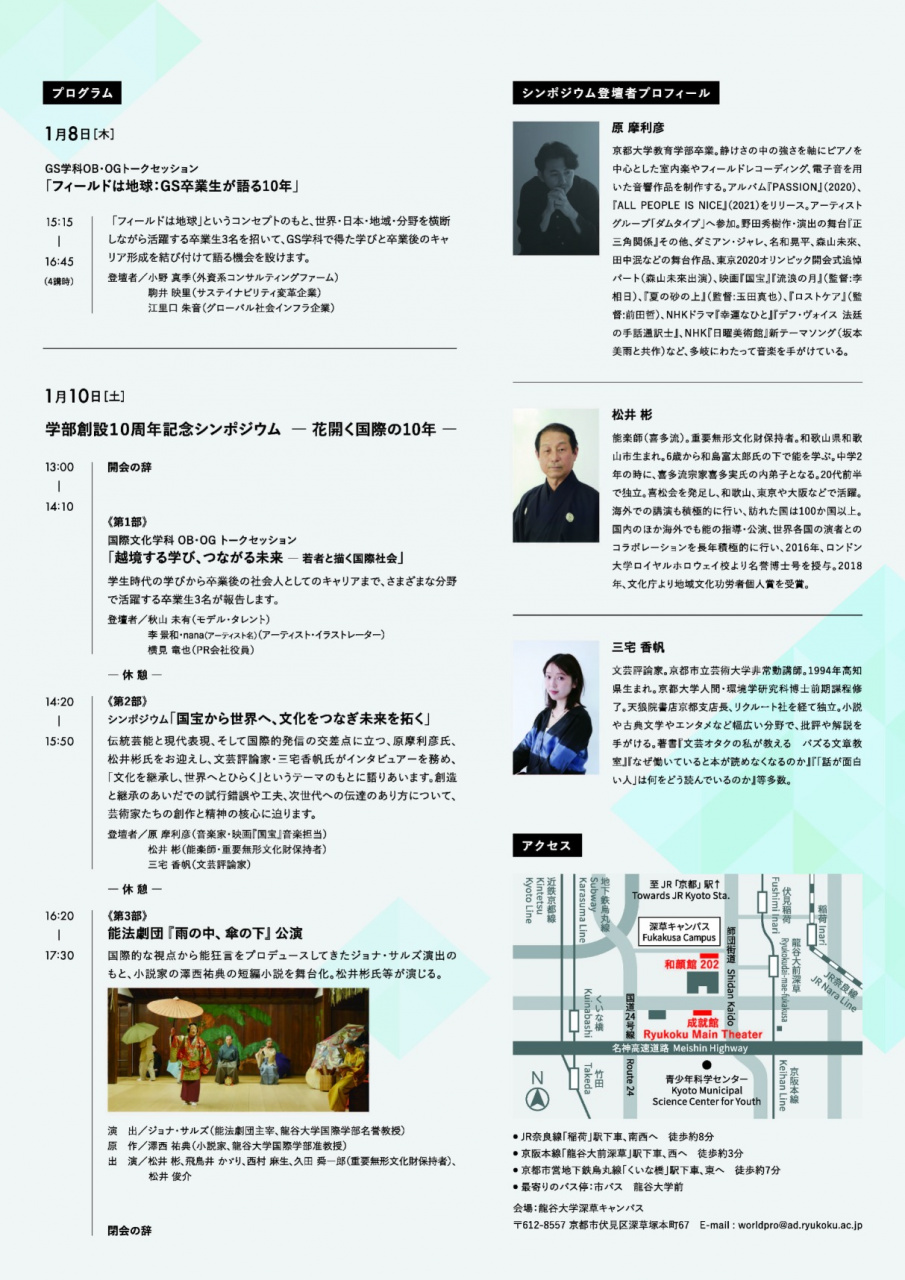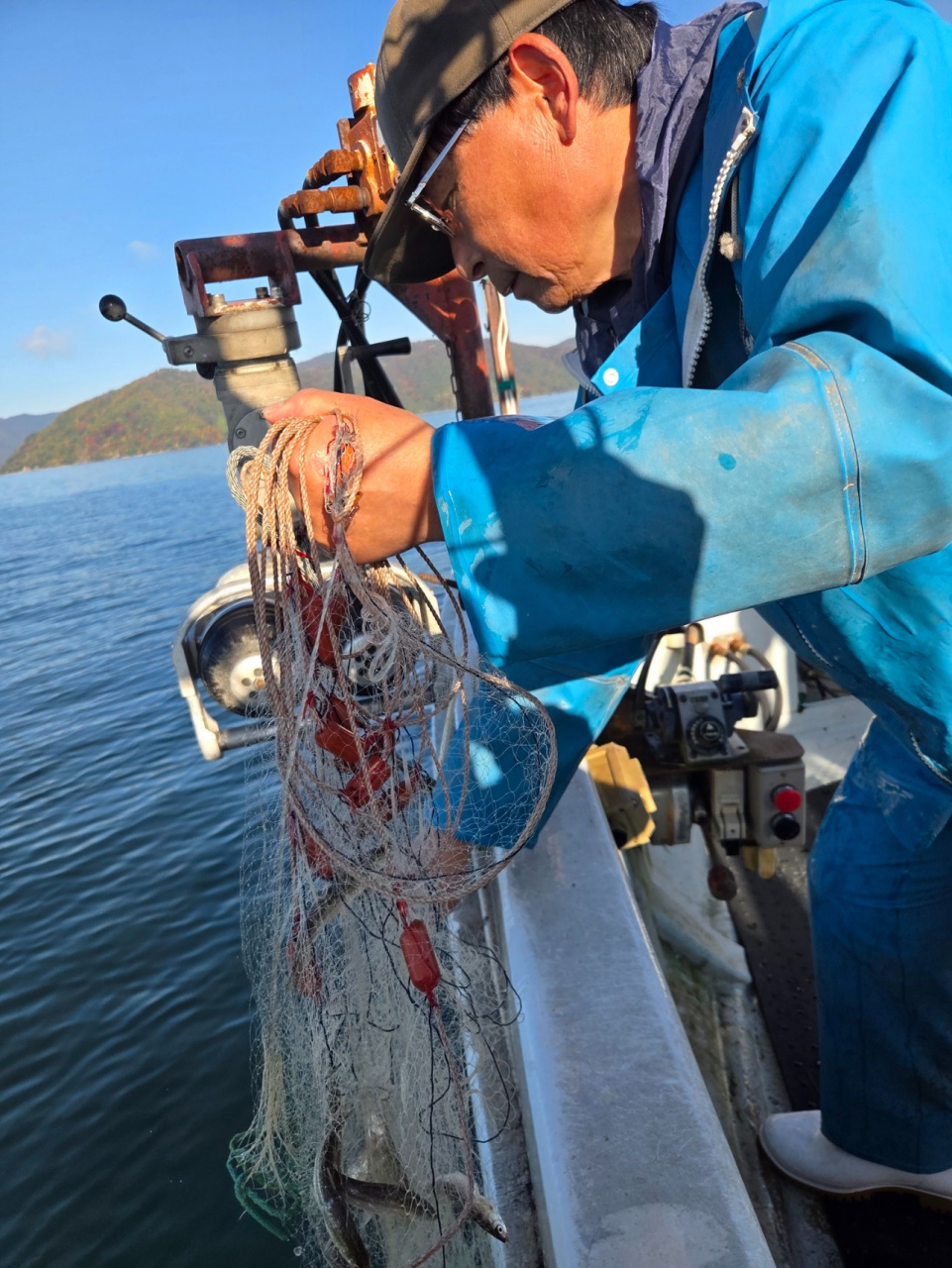実践真宗学研究科では、体系的な理論研究と実習を中心とした現場での活動を軸に、”理論と実践”を取り組んでいます。
実践真宗学研究科において重要な位置づけである実習について、毎年、「実習報告会」を開催し、修了生が実習の成果を研究科の内外に向けて発信しています。
今年度は、11月6日(木)に龍谷大学実践真宗学研究科 実習報告会を開催しました。
実習報告会の内容について、先輩たちの実習報告を聞いた、実践真宗学研究科1年生の学生の皆さんの声をもとにご紹介します。
1.「浄土真宗本願寺派における矯正教化の研究 ―教誨師の活動の実際―」
発表者:研究科3年 大塚さん
今回の大塚さんの発表では、浄土真宗本願寺派教誨師における活動の実際から教誨師として活動を続けられる動機とは何かについて、大阪刑務所、浄土真宗本願寺派矯正教化連盟、本派教誨師・篤志面接委員中央研修会での参与観察および教誨師、篤志面接委員の方への聞き取り調査をもとに発表していただきました。
はじめに、参与観察では、教誨師の活動の場である刑務所の現状や教誨師の方々との判別討議を通して、教誨師の側から見た刑務所の現状についてまとめられました。
次に、聞き取り調査を通して、活動を始める動機の部分に共通点があることを明らかにされました。そして、得た知見から活動を続けていく中での心境の変化に注目されました。その一つとして「いろんなことを考えさせていただける、そういう身に変わっていった気がします」という教誨師の方の声を挙げられていました。
発表を聴講する中で、「御同朋・御同行」の精神に基づき活動を行う教誨師の姿勢、教誨師の活動を行っていく中での心境の変化について強く述べられた姿が印象的でした。
(コメント 研究科1年 岡本さん)
2.「寺院の活性化に向けたソーシャルキャピタル活動の研究」
発表者:研究科3年 佐々木さん
今回の佐々木さんの発表では、寺院の活性化に向けたソーシャルキャピタル活動の取り組みについて、複数の寺院での実習経験をもとに報告されていました。お寺の後継者として暮らす中で直面する「地域関係の希薄化」や「寺院の衰退」といった課題に対し、実際の現場でどのような形で地域住民とのつながりを生み出しているのかが具体的に示されていました。
特に、実習先のそれぞれの寺院が地域の状況に応じて多様な活動を展開している点が印象的でした。コワーキングスペースの開放や、専門職と連携した相談事業、国際支援マーケットなど、各寺院のソーシャルキャピタル活動が寺院の活性化につながっていたという結論が示されていました。
また、住職の明確なビジョンの重要性や、小さな成功体験を積み重ねることの大切さといった考察は、今後自分が地域と関わる実習を検討する上でも大きな示唆となりました。寺院が社会の中で果たしうる新たな役割について、改めて深く考える機会となりました。
(コメント 研究科1年 山田さん)
3.「現代社会における真宗保育の実践に関する研究 ―保育者の宗教的情操に着目して―」
発表者:研究科3年 長岡さん
長岡さんの発表では、真宗保育の中心にある「まことの保育」の理念をもとに、子どもと保育者がともに育ち合うという視点を丁寧に示されており、とても印象深かった。子どもを一方的に“育てる”存在として捉えるのではなく、保育者自身も子どもとの関わりの中で気づき、揺れ、学びを重ねていくという姿勢が、具体的な実践例とともに語られていた点が特に心に残った。
また、子どもの行動や言葉を「指導すべき対象」として見るのではなく、そこに表れる思いや背景を受け止めることで、保育者自身の価値観が揺さぶられ変化していくという過程は、まことの保育が単なる理念ではなく、実践を通して深まる“関係性の学び”であることを示していた。
自分の研究でも寺院と若者の関係性を考えているため、人と人が出会い、関わる中で互いに変わっていくという視点は非常に参考になった。今回の発表を通して、保育の現場における「共に育つ」という姿勢の大切さを改めて実感した。
(コメント 研究科1年 藤範さん)
4.「死別に関するアンケート調査 集計結果報告」
発表者:研究科3年 廣田さん
今回の廣田さんの発表では、悲嘆に関する内容が非常に印象的でした。特に、悲嘆を抱える人の心の動きや、その背景にある喪失体験の深さについての分析や具体的な事例を通して、悲嘆というテーマの複雑さと人間の根源的な苦しみに改めて向き合うことができました。
発表を拝聴しながら、私自身の研究とも多くの共通点を感じました。在宅医療の現場においても、患者さんやご家族は身体的な痛みだけでなく、死別への不安や、これまでの人生や人間関係の喪失に深く苦しんでおられます。そのような悲嘆の現場において、宗教者としてどのように寄り添い、どのように支えることができるのかという課題は、私自身の関心とも深く重なります。悲嘆とは単なる「悲しみ」ではなく、人が「大切なものを失った」ことを受け止めようとする心の営みであり、その中には信仰や生き方の根底が反映されていると感じました。
私たち宗教者に求められるのは、悲嘆をすぐに癒したり、解決しようとすることではなく、その痛みをともに感じ、沈黙のうちに寄り添う姿勢を保つことだと思います。廣田さんの発表を通して、悲嘆にある人の言葉にならない思いに耳を傾けることの尊さ、そして宗教的な関わりの可能性を改めて考えさせられました。
(コメント 研究科1年 大久保さん)
5.「現代における地域社会と寺院の共生 ―ツーリズムの視点から―」
発表者:研究科3年 福間さん
福間さんは、現代社会と寺院の希薄化した関係性を鑑みて、ご自身の所属寺院のある地域が観光業中心の城下町であることを背景に、地域と寺院が「ツーリズム」から持続可能な共生関係を構築できるのではないか、という研究をされています。
本発表では築地本願寺、永明寺、微住の3つの事例を基に、地域と寺院の結びつくための糸口が模索されています。これら事例の共通点として、
1.ツーリズムをご縁のきっかけとして活用している。
2.地域と寺院の相互的な関係性の構築が図られている。
3.寺院空間を交流拠点として位置付けて、場所の「公共性」の活用がなされている。
と分析されました。
以上の点から、現代寺院において必要なのは「聖」の尊厳を保ちつつ「俗」なる多様な接点を持つ関係の柔軟性を持ち、さらに時間をかけ相互的な関係性を築くことで共生関係が構築できるのではないかとまとめられました。
(コメント 研究科1年 小泉さん)
今回の実習発表会を経て、発表者は、これまでの実習に対する手応えや修士論文の執筆に向けての気づきを得ることができました。
また、先輩たちの報告を聞いた学生たちは、今後取り組んでいく自らの実習に向けて、たくさんヒントを得られたことと思います。