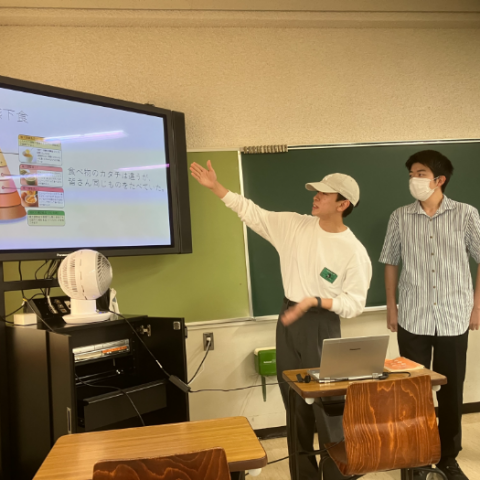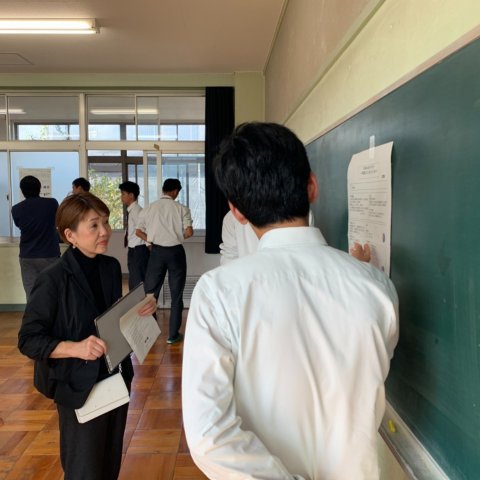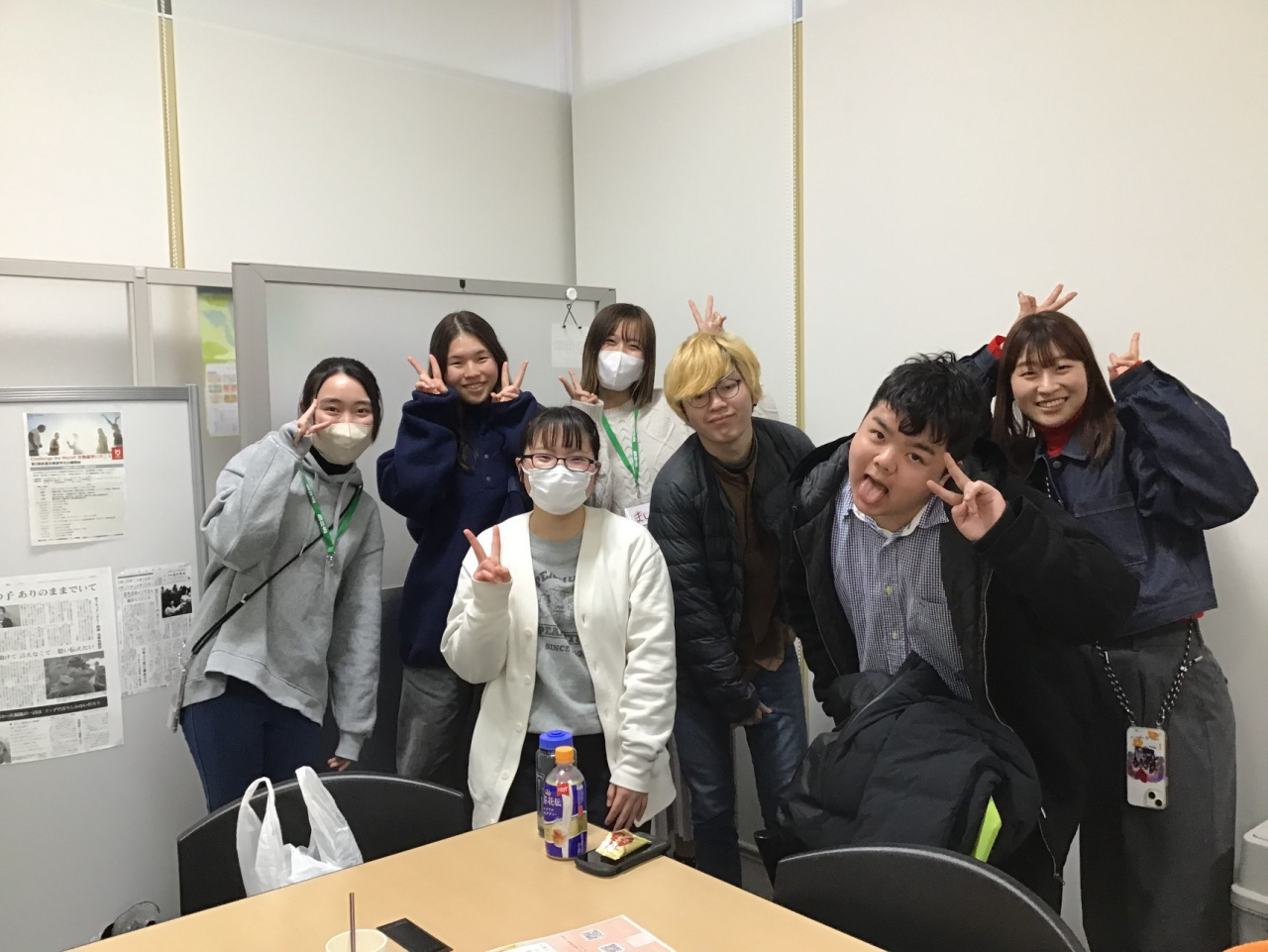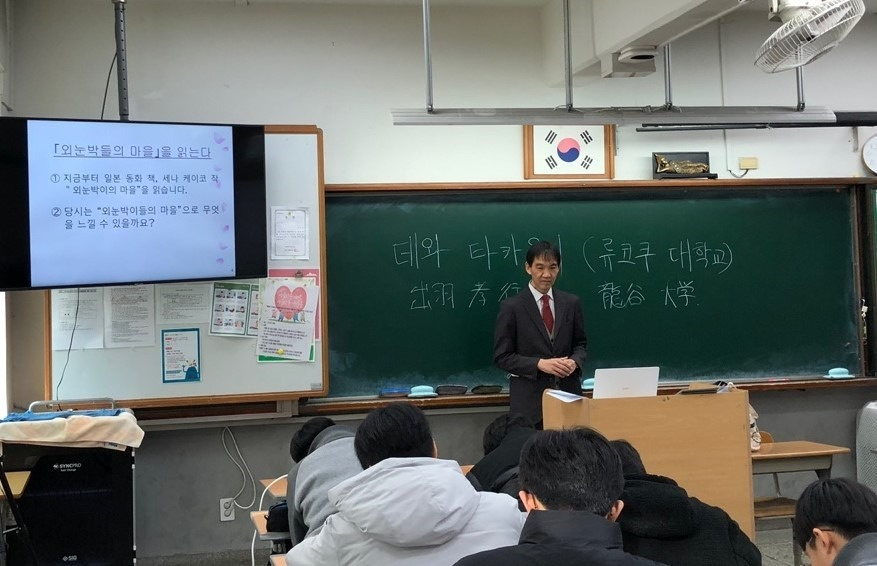令和6年能登半島地震の被災学生に対するご支援のお願い
Ⅰ.令和6年能登半島地震の被災学生に対するご支援のお願い
令和6年能登半島地震で被災された方々に、心よりお見舞い申し上げます。
被災地の皆さまの安全と安心が一日でも早く確保されますことを、心より念じております。
龍谷大学では、このたびの地震に関して1月2日付で学長名のメッセージを発出するとともに、被災した学生への各種奨学金等の支援を行っております。
これまでにも、東日本大震災や新型コロナウイルス感染症等の危機事象が発生した際には、多くの皆様からのご協力を賜り、在学生に対する各種支援を実施することができました。
このようなことから、このたびの地震に関しても、個人(教職員、学生、卒業生、保護者、一般)および団体(各教職員団体、各学生団体、各学部同窓会、関係法人)を対象に、被災学生に対する支援のための資金として募金活動を実施いたします。
多くの皆様のご協力を心よりお願い申し上げます。
Ⅱ.募金使途
(1)募金の名称
学校法人龍谷大学教育研究等振興資金 「危機事象対応学生支援募金」
(2)募金の目的及び使途
被災学生の修学支援と復興支援活動
(被災地での医療支援や学生・教職員等によるボランティア活動等)
Ⅲ.お申し込み方法
(1)インターネットからのお申し込みについて
インターネットからのお申し込みの場合、「クレジットカード決済」「コンビニ決済」「Pay-easy決済」から選択いただくことができます。
※募金手続き画面において、使途を選択できますので「危機事象が発生した際の学生支援に対応する「危機事象対応学生支援募金」」をご選択ください。
(2)ゆうちょ銀行「払込取扱票」によるお申し込みについて
本学所定の払込取扱票に、必要事項をご記入・ご捺印の上、最寄りの郵便局にてお振り込みいただけます。ご利用を希望される方は、以下までまでご連絡ください。
問い合わせ先
龍谷大学財務部経理課
TEL 075-645-7876
Mail keiri@ad.ryukoku.ac.jp
Ⅳ.募金の対象
(1)個人 教職員、本学学生、卒業生、保護者、一般
(2)団体 校友会、親和会、各学部同窓会、各教職員団体、関係法人(事業者等)
Ⅴ.募金金額
募金金額、口数等は定めておらず、任意とさせていただいております。
Ⅵ.募金期間
募金期間は設けておりません。
Ⅶ.領収書発行及び税額控除
学校法人龍谷大学発行の「寄付金領収証」を財務部経理課から送付させていただきます。
税法上の優遇措置の詳細については、以下のリンクをご確認ください。
https://www.ryukoku.ac.jp/contribution/tax.html
以 上