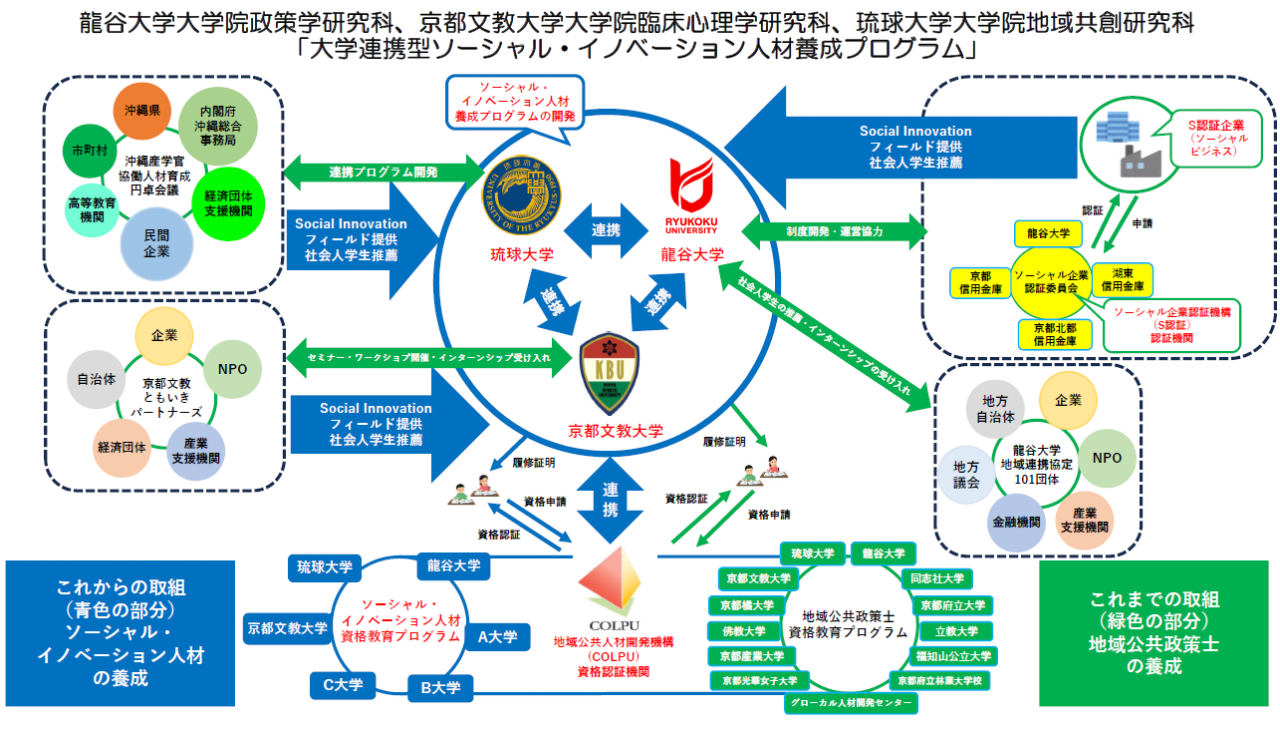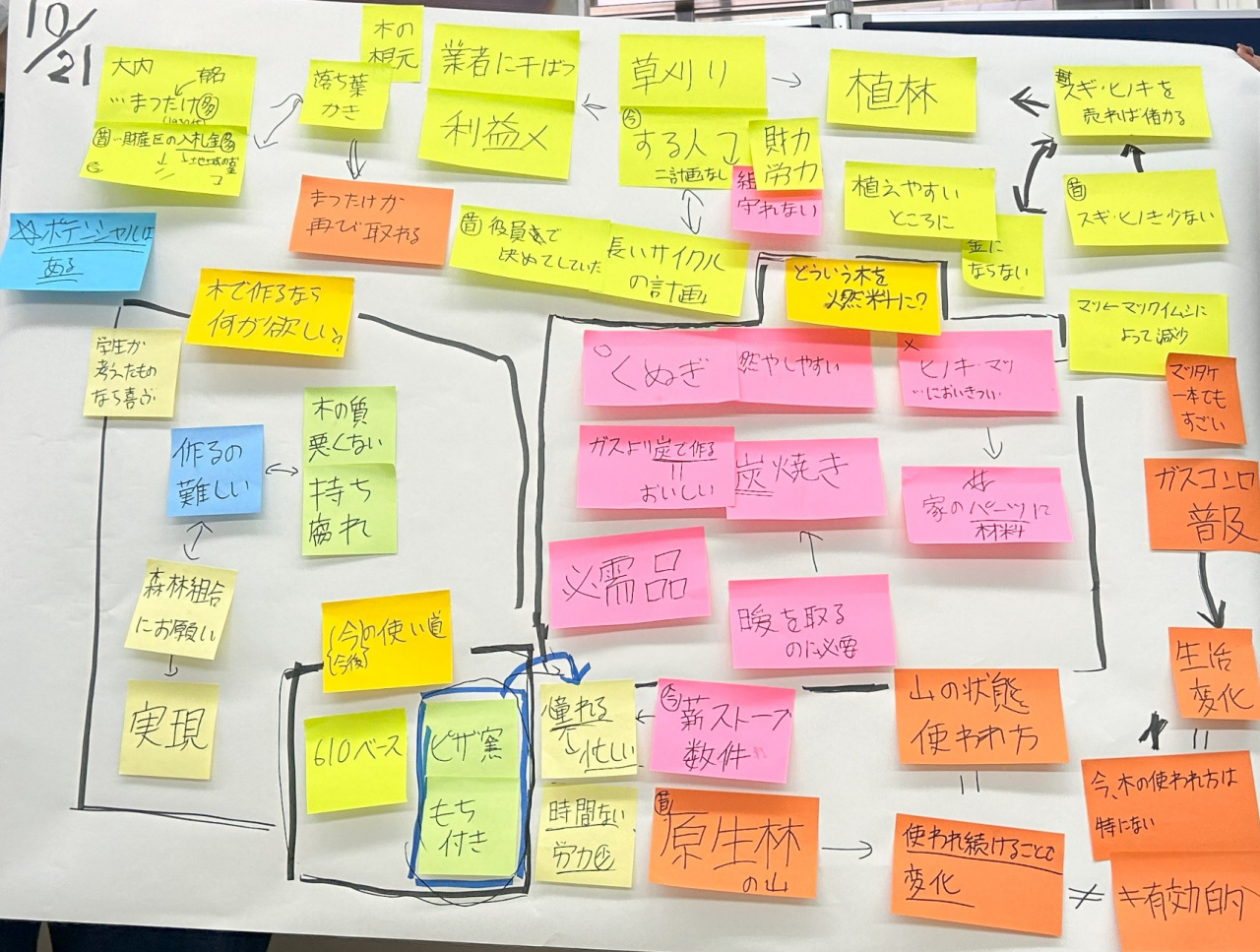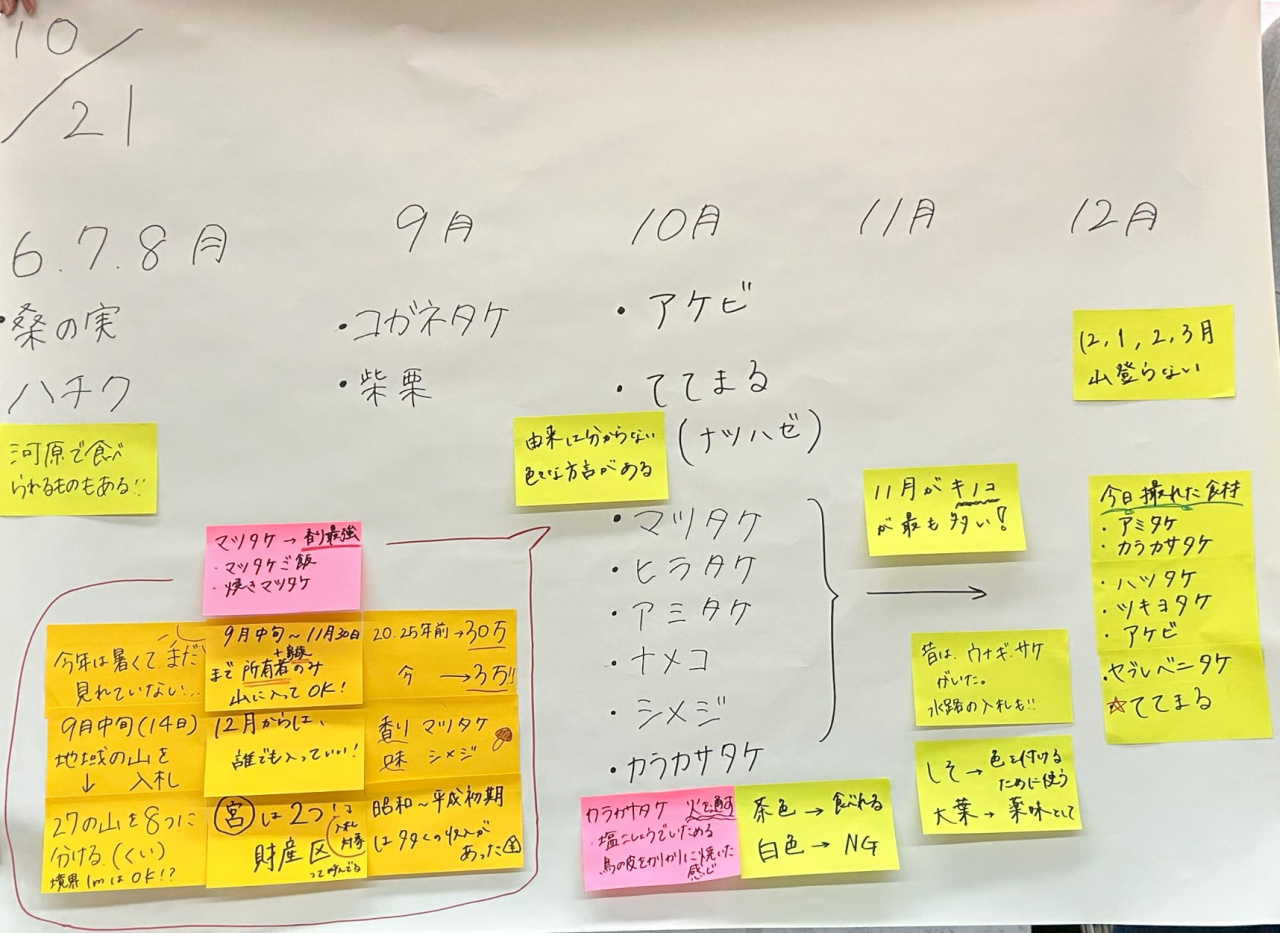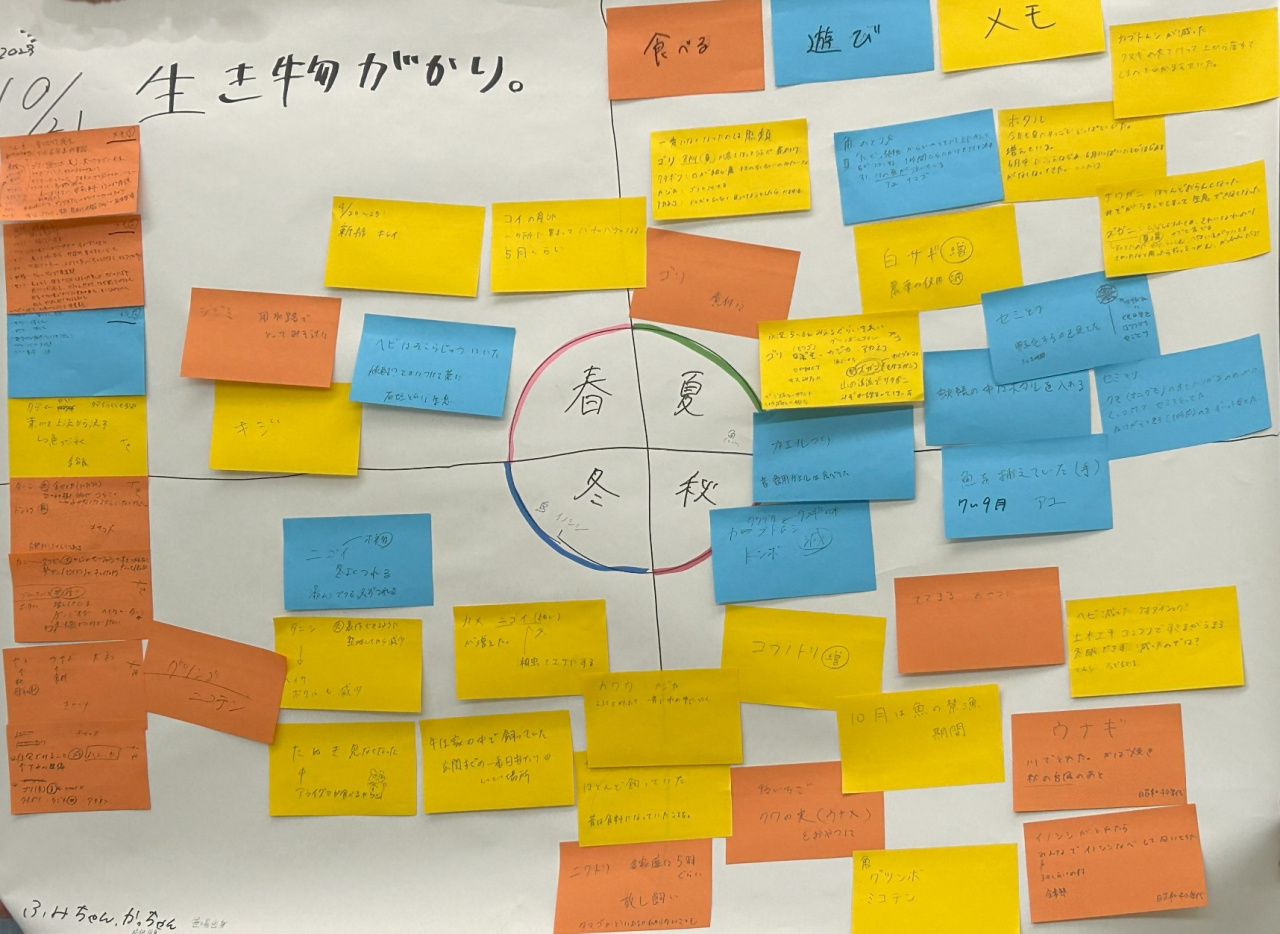農学部生の資格取得をサポート!「日本農業技術検定」合格証書授与式を開催【農学部】
7月8日(土)に「日本農業技術検定2級」の団体受検が実施されました。この団体受検は、農学部生の資格取得支援事業の一つとして2022年度より実施されています。
2022年度には全国平均を上回る合格率で、日本農業技術検定協会より「令和4年度日本農業技術検定団体受験」における優秀な成績を評価いただき、「2級優秀団体賞」を受賞しました。
今回実施の2023年度第1回は、全国の合格率が22.6%に対し、農学部農学科3年生受検者の合格率は27.4%と、今年度も優秀な結果となりました。
事前学習として、外部講師による「日本農業技術検定について」の講演もあり、受験対策のお話なども、合格率アップの大きな要因と考えられます。
10月11日(水)には合格証書授与式が執り行われ、竹歳農学部長より合格者一人一人に合格証書が授与されました。
竹歳農学部長からは「2級合格はとても素晴らしいことです。今後に生かすことのできる資格なので、ぜひ1級にチャレンジしてほしい。」
というお話がありました。最後には、合格証書を手に、晴れやかな表情で記念撮影をして表彰式は閉式しました。
※2022年度より農学部生の専門キャリアの資格取得支援として、日本農業技術検定2級団体受検を実施しています。受検を希望する農学部農学科3年生は、無料で受検ができます。また、事前学習として外部講師による講演会を開催しています。