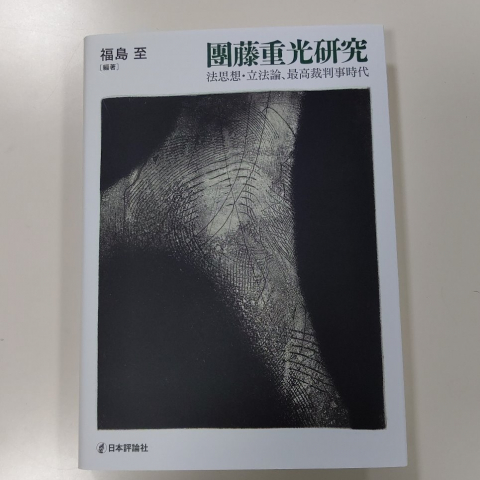【龍谷大学ATA-net研究センター/犯罪学研究センター共催・ティーチイン】 シリーズ第6回「裁判所は大麻の〈有害性〉についてどのように考えてきたのか」
龍谷大学 犯罪学研究センター(CrimRC)は、下記のウェビナーを、来る5月17日(月)に共催します。
【>>お申込みページ】
※お申し込み期限:5月17日(月)18:00まで
「裁判所は大麻の〈有害性〉についてどのように考えてきたのか」」
日時:2021年5月17日(月)18:00-20:00
形式:Zoom/定員:約200名
報告者:園田 寿(甲南大学名誉教授・弁護士)
プログラム ※一部変更となる場合があります
1.開会の挨拶 石塚 伸一(本学法学部教授) 5分
2.報告者 園田 寿(甲南大学名誉教授)55分
3.質疑応答・ディスカッション 55分
4.閉会の挨拶 5分
【企画の趣旨】
最高裁が昭和60年の2つの決定において、大麻の有害性を前提に大麻規制の合憲性を肯定して以来、大麻の有害性についての議論は少なくとも法廷の場では決着をみたといわれている。しかし、これは30年以上も前の議論であり、その後大麻に関する科学的研究も進み、国際的には大麻に対する寛容の度合いも進んでいる。このような流れの中で、改めて大麻取締法の成立過程や大麻の有害性に関する裁判所の考え方を検証する。
【プロフィール】園田 寿(甲南大学名誉教授・弁護士)
1952年生まれ。甲南大学名誉教授、弁護士、元関西大学教授。 専門は刑事法。ネットワーク犯罪、児童ポルノ規制、青少年有害情報規制、 個人情報保護などを研究。
主著に『情報社会と刑法』(2011年成文堂、単著)、『 エロスと「わいせつ」のあいだ』(2016年朝日新書、共著)など。
ヤフーニュース個人に連載中『罪と罰のはなし』http://bylines.news.yahoo.co.jp/sonodahisashi/
主催:龍谷大学 ATA-net研究センター
共催:龍谷大学 犯罪学研究センター(CrimRC)
※Zoomの視聴情報は、「Peatix」お申込み後に届くメール(自動送信)に表示されます。Zoom視聴情報を、他に拡散しないようお願いいたします。
また、申し込み名とZoomの名前を合わせていただくようにお願いいたします。
【龍谷大学ATA-net研究センター/犯罪学研究センター共催・ティーチイン】 シリーズ第6回「裁判所は大麻の〈有害性〉についてどのように考えてきたのか」 の続きを読む