ブラウザからレイアウト自由自在
Layout Module
ここにメッセージを入れることができます。
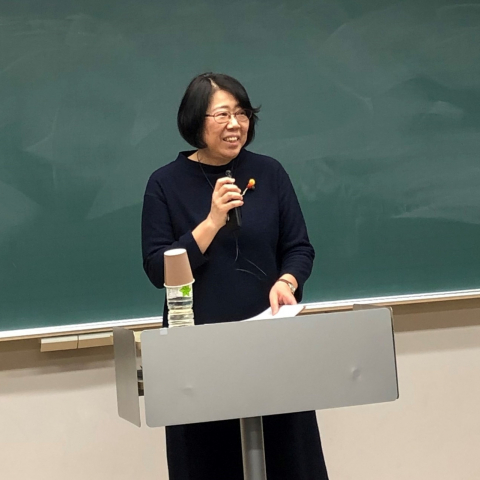
図書館司書課程 特別講義「図書館司書としてあるべき姿 ~民主主義と図書館~」の開催【文学部】
文学部開講科目「図書館サービス概論」では、図書館サービスの考え方と...

【犯罪学Café Talk】伊東 秀章講師(本学文学部/犯罪学研究センター「対話的コミュニケーション」ユニット研究員)
犯罪学研究センター(CrimRC)の研究活動に携わる研究者について、気軽...
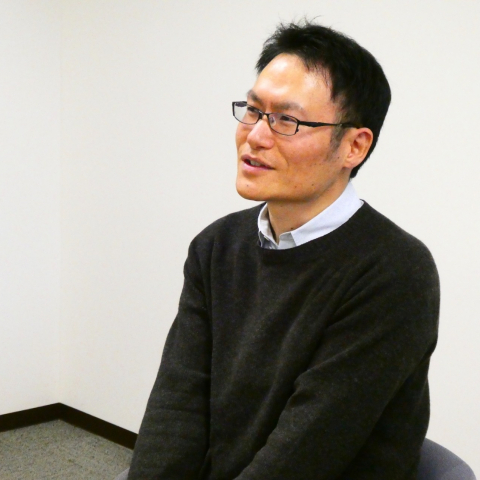
【犯罪学Café talk】佐々木 大悟准教授(本学短期大学部/犯罪学研究センター「矯正宗教学」ユニット研究員)
犯罪学研究センター(CrimRC)の研究活動に携わる研究者について、気軽...

新春シンポジウム「グチコレ&臨床宗教師―反省と挑戦」の開催【文学部】【実践真宗学研究科】
新春シンポジウム 「グチコレ&臨床宗教師―反省と挑戦」 主催:龍谷大学...


大学院奨励給付奨学金予約採用決定通知書の授与式実施【文学部】【実践真宗学研究科】
本学学部から本学修士課程に入学する方を対象に、進学を奨励することを...
龍谷大学政策学部は2020年に政策学部設立10周年を迎えました。政策学部・政策学研究科10周年を記念し、政策学部イメージ楽曲「ツナガル」と、楽曲にあわせた学部プロモーションビデオ(以下、PV)「龍谷大学政策学部・政策学研究科10周年記念 プロモーションビデオ」を制作しました!!
コロナ禍のいまだからこそ、『チーム政策※1』のつながりやここで学ぶ喜びと楽しさをPVで表現しようをテーマに、在校生・卒業生・教員・職員が出演、大学に関わりの深いクリエイター陣が制作を担いました。
<出演者・制作陣について>
出演者は在学生、教員、職員等です。異動した職員や、卒業生・院の修了生、それぞれの道を歩む卒業生・修了生も参加しています。
出演した卒業生の中には、在学中や卒業と同時に社会的企業を起業した、「アカイノロシ」(フェアトレードコーヒー)、「革靴をはいた猫」(障がいのあるスタッフが靴磨き・修理職人として活躍)、「Re-Social」(獣害をもたらすシカをジビエとした加工・流通(撮影当時は在学生))のメンバーも参加しています。
学生については、コロナ禍で卒業式が中止になった4年生や、入学式が中止となり「まだ大学生らしいことができていない」想いをもつ1年生等も参加。学生サポーターズやゼミ、大学院生が参画しています。
制作は政策学部の地域連携活動でつながったディレクター、大学院修了生であるダンスファシリテーター、卒業生の撮影・編集者と、大学とつながりのあるクリエイター陣が担いました。
<みどころ>
多様な専門性を扱う政策学部の特色を表現するため、多種多様にある「花」をモチーフとし、まさに「これから花開く」存在である学生たち(それぞれの花)が、開花していくことをイメージし制作しました。ストーリーは、今回のコロナ禍で企画が中断したことを受け、「困難で学びや取り組みが眠りについたように中断されることもあるが、そこからもう一度目覚めよう」、そんなストーリーになっています。
当初、2020年夏の完成を目指していたPV制作はコロナ禍により、中断を余儀なくされました。大学の対面講義が始まった後期に撮影を再開し、龍大政策学部はいち早く、学外活動を行うゼミやフィールドワーク授業向けに学生負担無料のPCR検査実施体制を整え、撮影スタッフにもこのPCR検査を実施しました。当日は検温・アルコール消毒、カメラが回っていないときのマスク着用を徹底した上で、撮影を行いました。
1年生の基礎演習や、2、3年生のクラスサポート委員会、学部の魅力を伝える学生イベントスタッフ、ゼミ、大学院生、卒業生など、幅広く声をかけて出演者を募集し、撮影当日の運営サポーターズも組織しました。
<楽曲について>
政策学部の成立以来のコンセプト「チーム政策」や「つなぐ」キーワードをイメージして、学生たちと年齢の近いニューウェーブ系ポップバンド「宇宙団」が政策学部のために「ツナガル」を作詞・作曲・演奏しています。
楽曲制作では実際に来学し、大学や学生の様子をご覧いただき、学部のコンセプトや学びの特徴、「チーム政策」「つなぐ(つなぎ・ひきだす)」といったキーワード、イメージを共有しました。コロナ禍前に制作したものですが「いまだからこそ」響く歌詞、曲となっています。この楽曲を今発信したいということも企画再起動の一因になりました。
<用語説明>
※1『チーム政策』
創設以来の政策学部のコンセプトです。「学生のための学びの環境」を教員・職員でつくり、そこに主人公である学生がいる。『チーム政策』はその学生・教員・職員による学びのコミュニティであることを表現しています。PVは、まさにこの「チーム」で作られました。
※2 「宇宙団」
作詞作曲を依頼。楽曲である「ツナガル」(別紙歌詞参照)の作詞・作曲は「宇宙団」の望月シホ氏(教員の前任校での教え子というつながり)。「宇宙団」とは、HPでは、「東京の5人組ニューウェーブ系ポップバンド。Vo.gt.もちづきのまっすぐに伸びる声と、ニューウェーブ、あるいはプログレの風味を纏った捻くれサウンドにより、どこか耳に引っかかる、色彩豊かで類い稀な宇宙団流ポップスを確立している」と紹介されています。
農学部 食品栄養学科 管理栄養士養成課程助手の杉山紘基先生が、第19回日本改善学会近畿支部会学術総会における公衆栄養・栄養疫学部門において、若手研究者表彰を受賞されました。
杉山先生は、「大学生の食事時間分布評価および食習慣評価指標としての検討」を演題に報告しました。食事の内容に加えて、「いつ食べるか」も健康に関係していることが知られている一方で、「どの時間帯に食事をしているか」を具体的に調査した研究は少ない実情から、大学生を対象に食事時間のデータを解析し、食事時間の分布と食事回数の傾向を検討されました。本研究で検討した手法が、様々な集団の食習慣評価に活かすことができると期待されます。
【参考】
・第19回日本改善学会近畿支部会学術総会HP
・杉山 紘基 先生
2021年2月26日(金)、福井県の企業等への就職を希望する学生の支援、就職促進を目的に、就職支援に関する協定を締結しました。
本協定は、本学と福井県が相互に連携・協力し、学生に対し福井県内の企業情報等を提供するなど、就職活動を支援することにより、企業への就職促進を図ることを目的とするものです。今回、協定を締結することで、福井県への学生の就職先をさらに拡大し、学生への就職支援を強化いたします。
福井県との就職支援協定 連携協力事項
(1)学生に対する県内の企業情報、各種イベント等の周知に関すること。
(2)学生に対する福井県で暮らすメリットや魅力の説明等に関すること。
(3)学内で行う合同企業説明会等の開催に関すること。
(4)保護者向けの就職セミナーの開催に関すること。
(5)学生のU・Iターン就職に係る情報交換および実績把握に関すること。
(6)県内企業等における学生のインターンシップ受入の支援に関すること。
(7)県内企業の採用活動の支援に関すること。
(8)その他、学生のU・Iターン就職促進に関すること。
龍谷大学の就職支援協定締結(18府県)
近畿地方3県(京都府、滋賀県、三重県)、中国地方5県(鳥取県、島根県、広島県、岡山県、山口県)、四国地方4県(徳島県、香川県、愛媛県、高知県)、北陸地方2県(石川県、福井県)、中部地方1県(長野県)、九州地方3県(福岡県、熊本県、鹿児島県)、との間に、就職に関する協定を締結しています。