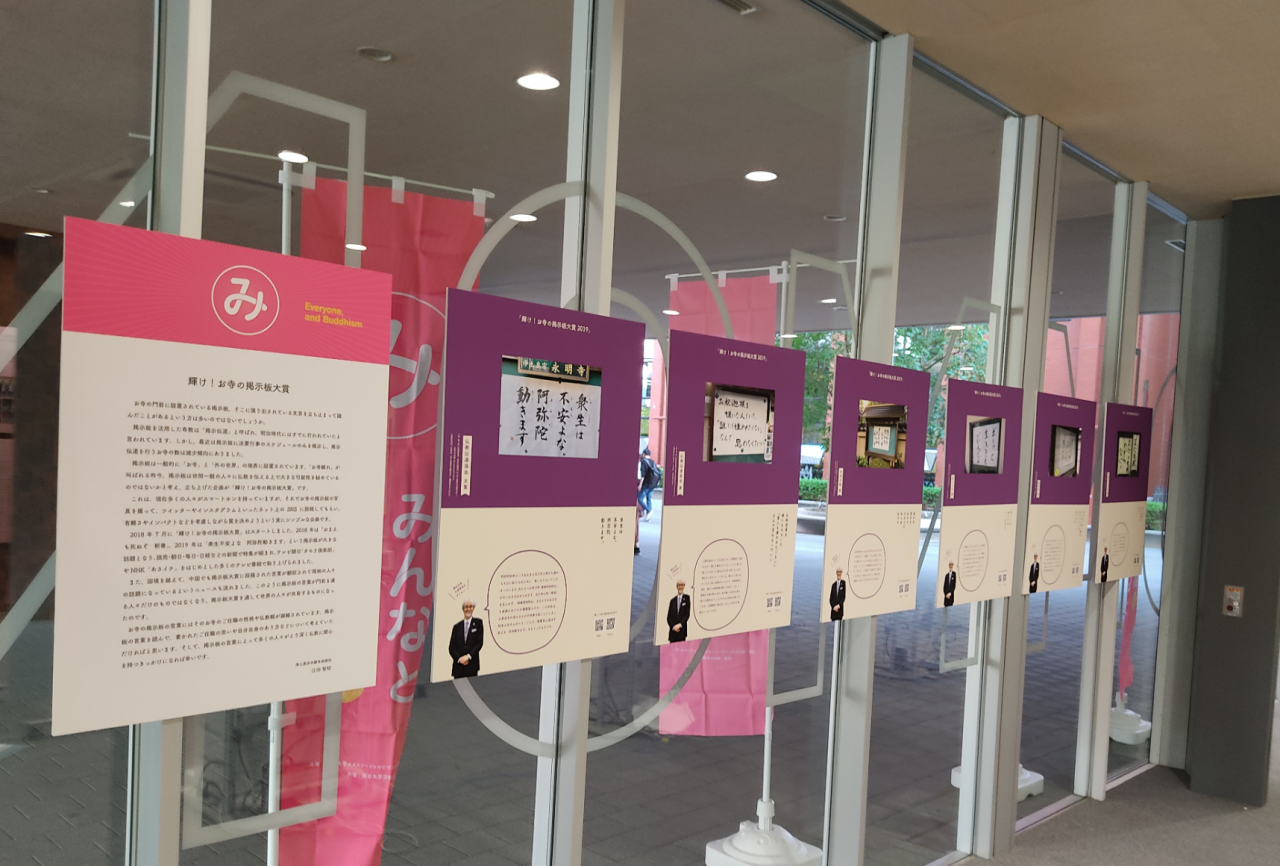「マナー講座」を開催しました!【社会共生実習】
社会学部には、全3学科が共同して運営する「社会共生実習」という実習があり、そのサポート業務を担う社会共生実習支援室があります。
社会共生実習支援室では、「社会共生実習」の受講生やその他の社会学部の学生向けに講座や講演会などを開催し、学生のスキルアップを図っています。
「社会共生実習」は学外での活動が多く、大学関係者以外の方と学生が接する機会の多い実習なので、受講生らには節度ある行動が不可欠です。そこで、受講生の礼儀作法向上を目的として、毎年、「マナー講座」を開催しています。
例年であれば、年度初めに開催しますが、今年はコロナ禍によって前期の学外活動がほぼ叶わなかったため、後期が開始して間もなくの9月25日と10月2日にオンラインツールにて開催する運びとなりました。
今回の「マナー講座」に参加した学生からは、「今後必要になってくる大切な内容であったため、とてもためになりました。これからの実習活動に役立てていきたいと思います。」、「今まで知らなかったマナーがたくさんありました。勉強したことを、身近なところからどんどん活用していきたいです。」というような声がありました。
社会共生実習支援室では、今後も学生のスキルアップにつながるような講座や講演会を企画立案・運営して参ります。
社会学部「社会共生実習」について、詳しくはこちらの【専用ページ】をご覧ください。