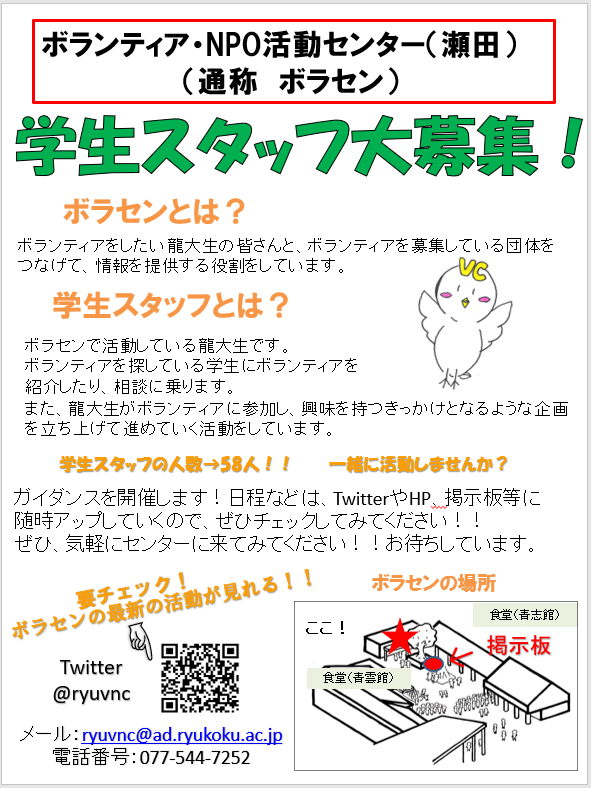10/1から大学見学会を再開、相愛中学生が深草キャンパスを見学【高大連携推進室】
対面授業で学生が戻りつつある中、10月1日から高校生等を対象とした大学見学会の受け入れを再開いたしました。
10月2日には、宗門関係校である相愛中学校2年生と教員約40名が深草キャンパスを訪問。顕真館での朝の勤行に続き、和顔館にて大学についての説明とミニキャンパスツアーを体験しました。大学の施設を見学した生徒は「とにかく広くて食堂がいっぱいあって楽しそう」と感想を口にしていました。
コロナ禍の見学会の受け入れは、40人以内で90分以内の実施と条件付きですが、大学を知っていただく貴重な機会ですので、換気や消毒などコロナ対策を行いながら、高校生の大学理解に貢献できるよう今後も取り組んでまいります。

大学説明を受ける相愛中学の生徒(和顔館アクティビティホール)