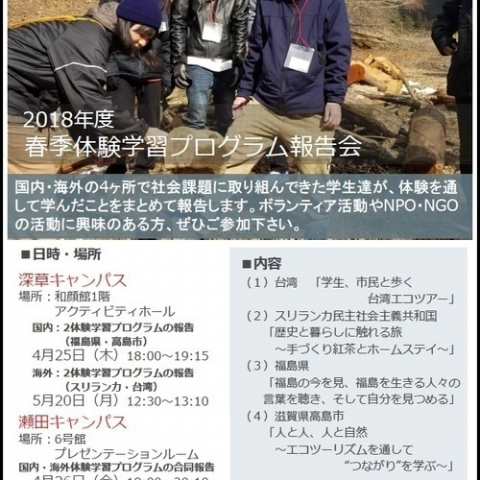社会福祉学科・オンライン新入生歓迎会を開催
社会福祉学科 新入生交流進んでいます!
2020年度のスタートは、「新型コロナウイルス流行」一色で始まりました。入学式の中止、前期すべてオンライン授業と、かつて経験したことがない出来事ばかりです。
そんな中でも、龍短社会福祉学科の学生たちは、何とかつながりを作るためにがんばっています。
2年生の藤田悠斗くんが中心になって、新入生オンライン交流会を開催してくれました。
第1回 オンラインランチ交流会(5/26)は1年生50人、2年生11人が集まりました。
第2回 オンライン交流会(6/13)は25人が集まりました。
第2回は、第1回目で希望が多かった1年生同士の交流の機会を大切にしました。オンライン上でグループを作り、自己紹介、他己紹介、共通点探し等、少人数から複数の人数まで、グループを変えて交流しました。
最後はグループラインにつながるためのQRコードを紹介し、終わりました。
藤田くんは、Twitter(龍短社福サポート)を開設し、その中の質問箱から新入生の質問を受け付けています。そこには30人くらいの新入生のアクセスがあるようです。
新入生の中にはTwitterでつながり、そこからグループLineができ、電話し合える友だちができたと話す人もいるようです。
龍短の輪が広がっています!
次回オンライン交流会第3弾(6/27)も実施予定です!