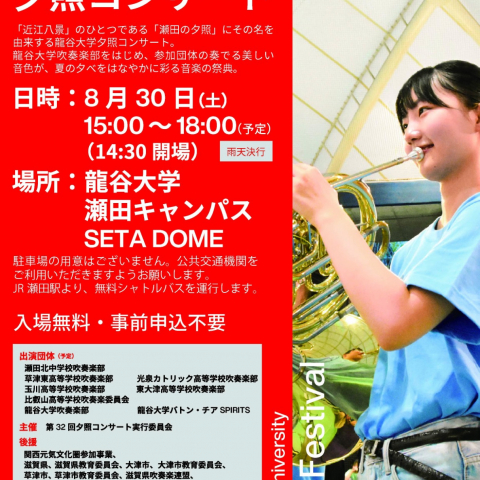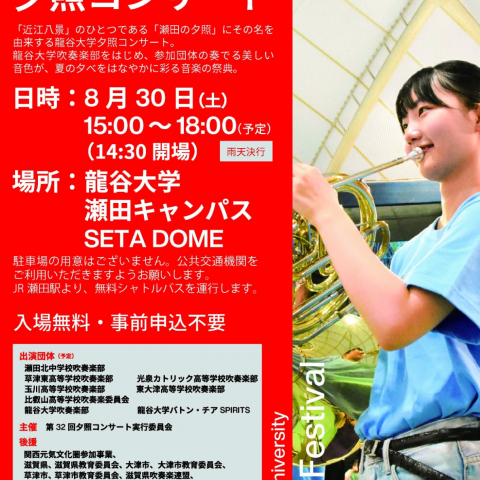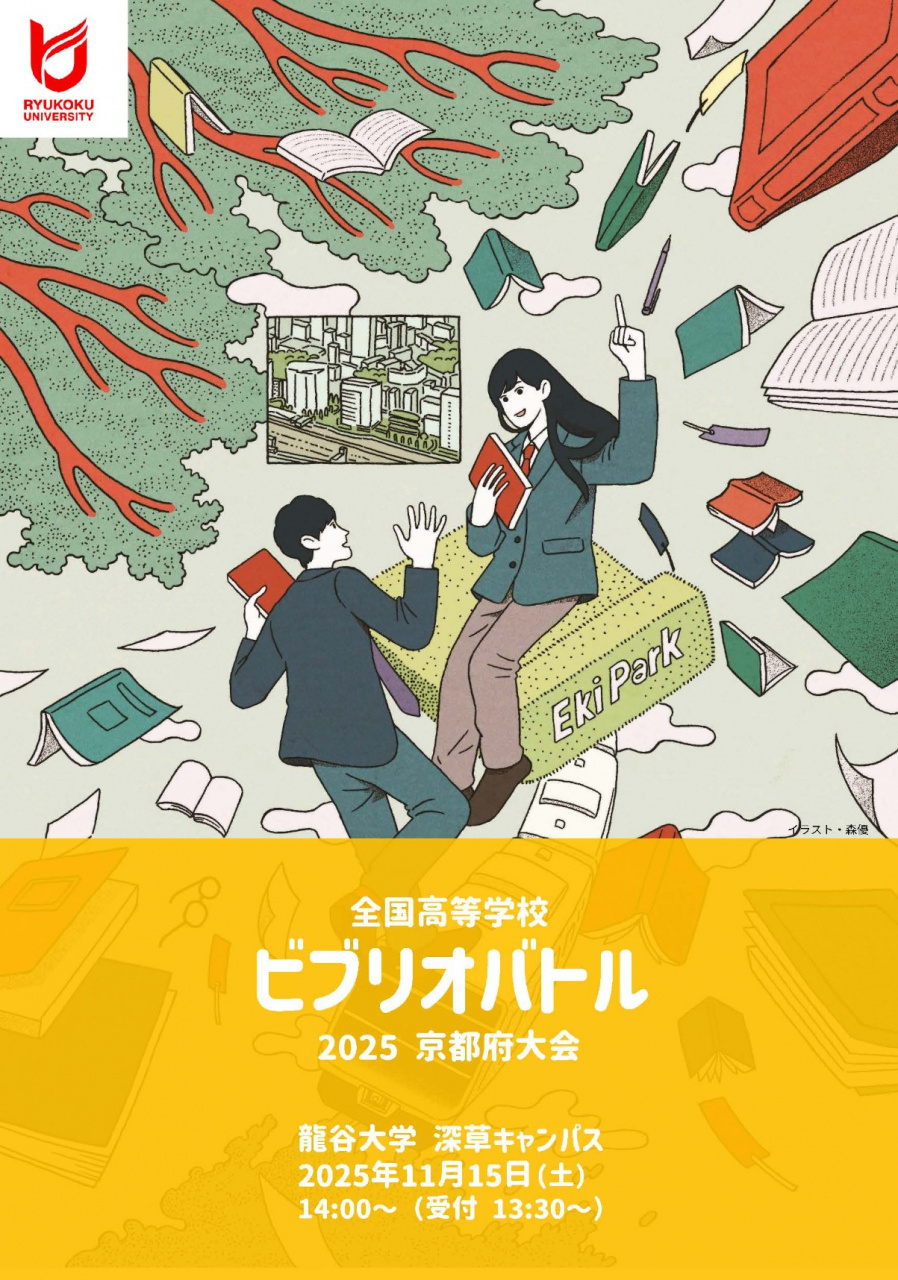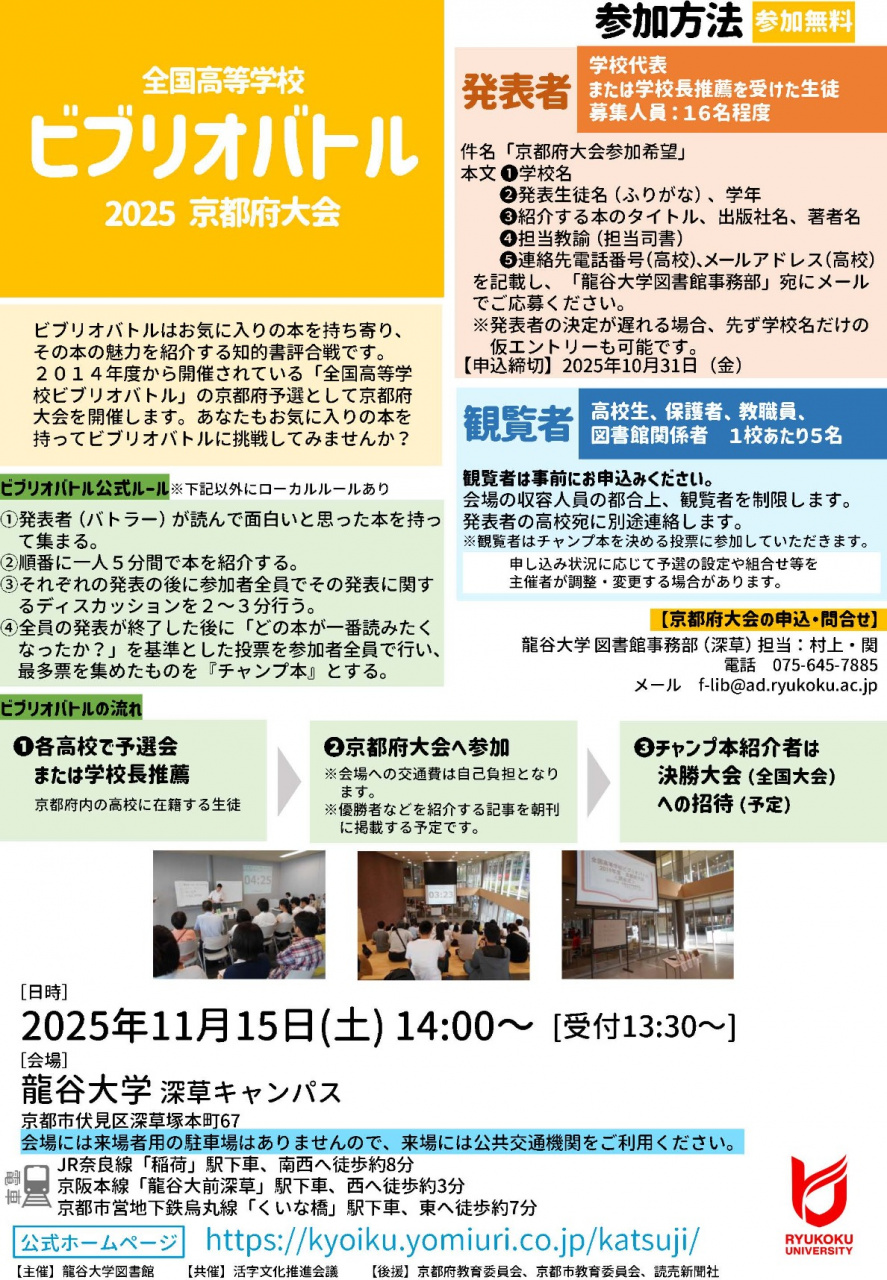学生レポート・海外中国語研修講座2025 in 上海-観光編【R-Globe】
〈蘇州の日帰り旅行について〉
私たちは、日帰り旅行で蘇州を訪れました。日本語ガイドの方が同行してくださり、主に歴史について詳しく説明していただきました。
蘇州では、虎丘(こきゅう)にある雲巌寺塔を見学し、山塘街(シャンタンジエ)を軽く散策した後、网师园という庭園を訪れて景観を楽しみました。
虎丘の雲巌寺塔は7階建てで、1階から6階までは右に傾き、7階だけが左に傾いているという、とても珍しい構造をしています。これは、それぞれの階が改修された時期が異なることが理由だそうです。実際に目の前で見ると、その大きさと迫力に驚かされました。
山塘街では、昔ながらの街並みが残っており、多くのお土産屋さんが立ち並んでいます。私たちは乗りませんでしたが、小舟に乗って運河を巡る観光客も多く、風情ある景色を楽しめる場所でした。
网师园では、美しい庭園と建物の雰囲気に癒されました。歴史を感じる静かな空間で、写真を撮るのにもぴったりな場所でした。
昼食は、ターンテーブルのある中華料理店でいただきました。たくさんの種類の料理が並び、どれもとても美味しかったです。
この日の最高気温は39度と非常に暑かったのですが、普段見ることのできない建物や景色を実際に見ることができ、とても充実した一日となりました。蘇州の有名な観光地を一気に巡ることができたため、ややスピード感のある旅でしたが、その分多くのものを見て回ることができました。
また、蘇州ではチャイナドレスや古代王朝風の衣装のレンタルも行われており、とても華やかで魅力的でした。次回は個人的に訪れて、そういった体験もしてみたいと思います。とても素敵な場所なので、ぜひ一度は訪れてみることをおすすめします。(政策学部 O.H)




〈フリータイムの過ごし方について〉
フリータイムには、各自で調べた観光地やお店を訪れました。主な移動手段は地下鉄でしたが、バスやタクシーを利用していた学生もいました。
訪れた場所は、大きなショッピングモールや有名なカフェ、上海ディズニーランドなど多岐にわたります。他にも動物園など、たくさんの観光スポットがありました。
食事は基本的に各自で用意する形でしたが、夜はみんなで火鍋や小籠包を食べに行くなど、グループで楽しむことも多かったです。また、中国の電話番号が必要にはなりますが、学校に出前を頼んだりもしました。
学校の敷地内にはスポーツのできる施設があったため、近くのスーパーでボールを購入して、みんなで遊ぶ時間もありました。
フリータイムの時間が多くあったので、事前に行きたい場所を調べておくとスムーズに行動できると思います。地下鉄やバス、タクシーもアプリに登録すれば簡単に利用でき、とても便利でした。
学校の中だけでなく、周辺の街並みも日本とは異なっていて、ただ歩いているだけでも新鮮で楽しかったです。学校から少し歩けば、コンビニやスーパー、ご飯屋さんがあり、生活面でもとても過ごしやすかったです。
中でも個人的に印象に残っているのは、上海ディズニーランドです。チケットは早めに購入すれば少し安くなるので、おすすめです。とにかく暑いので、暑さ対策は必須です。上海ディズニーには「ズートピア」エリアがあり、ここでしか見られない建物や食べ物、中国語で話すキャラクターたちなど、すべてが新鮮でとても楽しかったです。
フリータイムを通じて、クラスメイトとの仲もより深まり、毎日がとても充実していました。どれも良い思い出ばかりで、忘れられない経験になりました。(国際学部 Y.A)