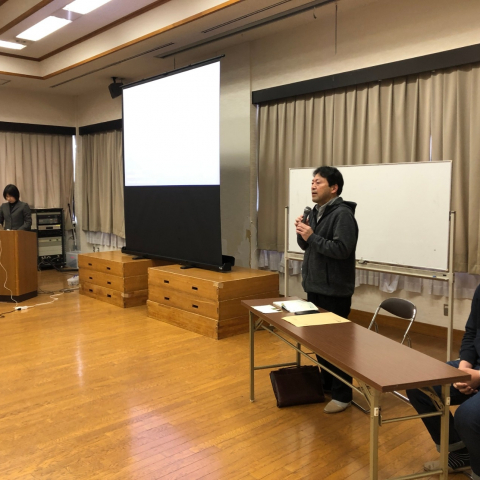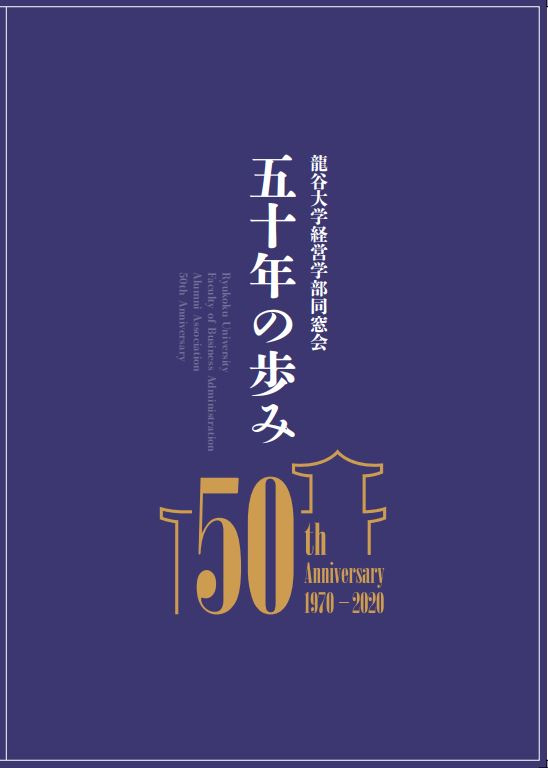(発表)一部科目の対面授業からオンライン授業への授業形態の変更について
現在、新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかからず、医療体制もひっ迫しています。このような状況も踏まえ、本学では感染防止対策を強化する必要があると判断し、「新型コロナウイルス感染防止のための龍谷大学行動指針」の活動制限レベル全体を4月19日(月)から当面の間、「レベル1」から「レベル2」に引き上げ、現在実施している対面授業の一部をオンライン授業に切り替えることといたしました。
現在、オンライン授業に授業形態を変更する科目について検討しています。感染防止とオンライン授業への変更準備のため、4月19日(月)から4月24日(土)の期間、一部の授業科目を休講いたします。休講する該当科目の詳細は、4月16日(金)中にポータルサイトに掲載しますので確認ください。
一部科目の対面授業からオンライン授業への変更は、4月26日(月)から当面の間とします。オンライン授業に変更する科目については、決定次第ポータルサイトからお知らせしますので留意ください。
会食による感染が懸念されています。昼食時の黙食を徹底してください。また、コンパや多人数での会食は厳に慎んでください。ご自身の「いのち」を大切にすること、ご家族や友人など大切な人の「いのち」を大切にすること、厳しい状況におかれ力を尽くしてくれている方々に感謝することを忘れず、龍谷大学生として責任を持った行動を心がけてください。
【感染予防対策】
本学では、感染防止対策として既に次の取り組みを実施し、感染予防に努めています。
・ソーシャルディスタンスを確保した教室定員(SD定員の設定)
・SD定員に基づく予備事前登録
・すべての対面授業での座席指定
・学生の皆さんへの除菌シート配布
・食堂でのアクリルパーティションの設置と抗菌処理
2021(令和3)年4月16日
龍谷大学・龍谷大学短期大学部