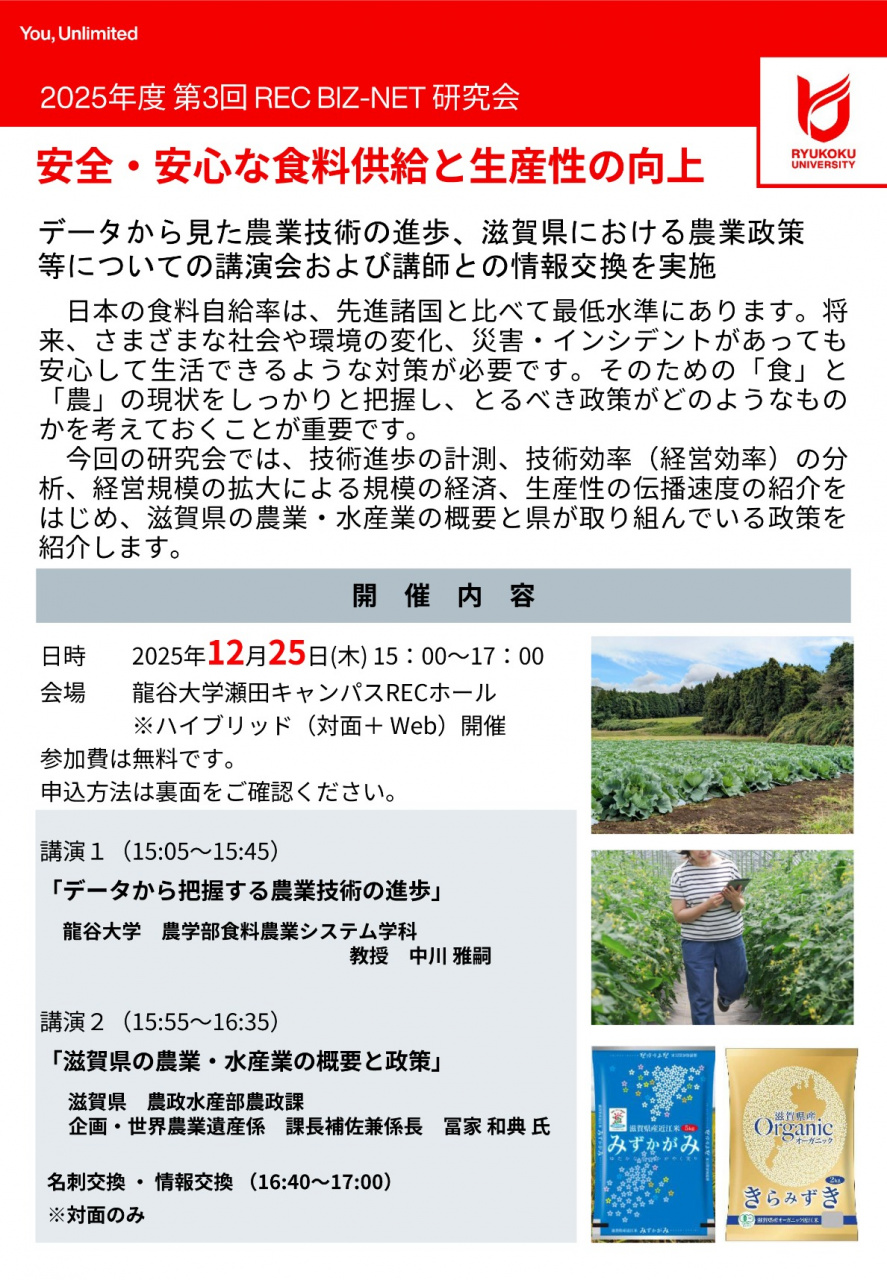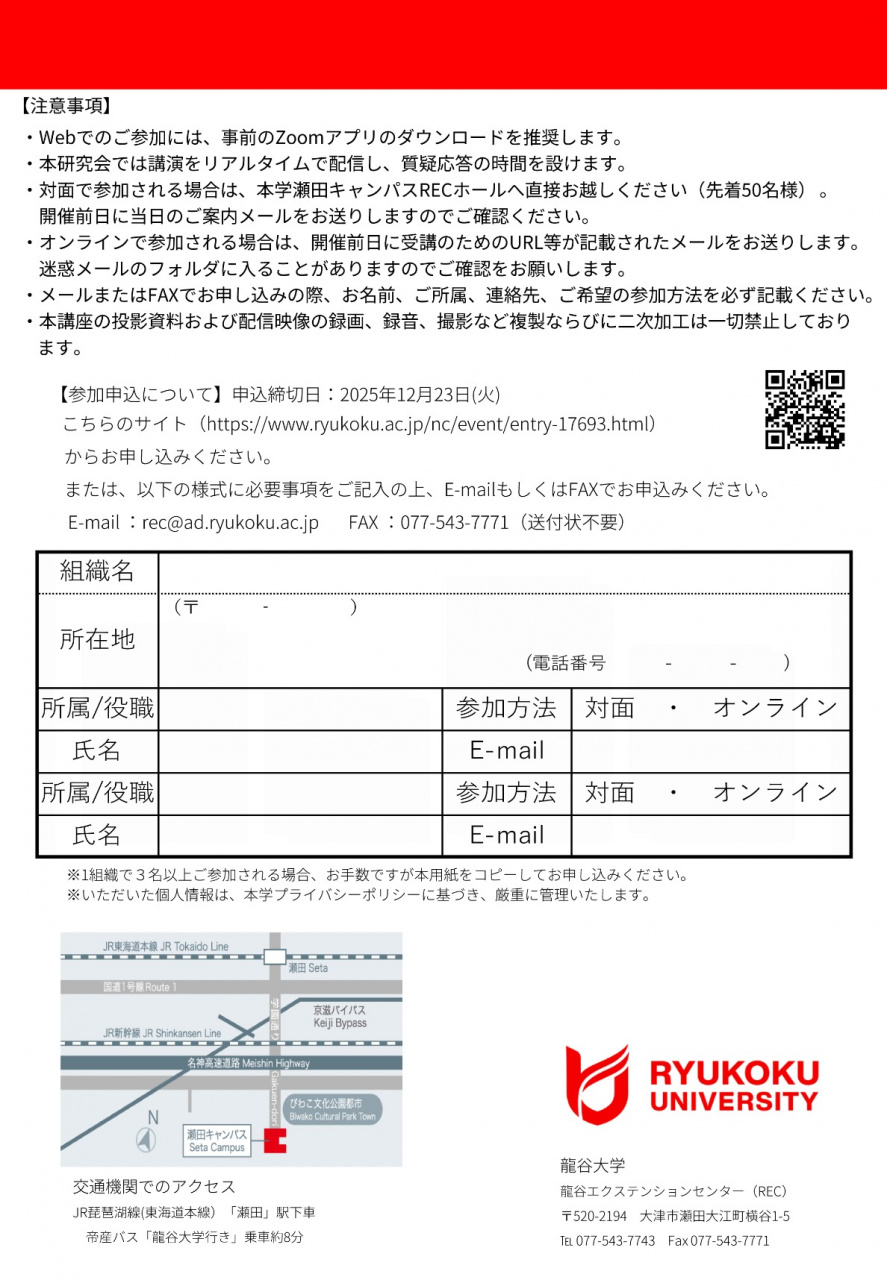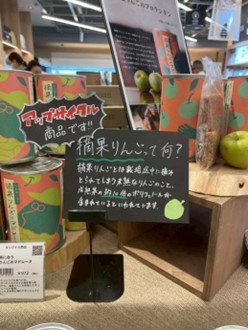2025(令和7)年11月18日大分市佐賀関の大規模火災に伴う災害で被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。
被害にあい、学費支弁が困難となった世帯の学生からの各種奨学金等の受付を次のとおり行いますので、学生部(深草・瀬田)までご相談ください。
また、学生本人やご家族が被災された方は、学生部(深草・瀬田)またはCampus HUB(先端理工学部・農学部・短期大学部は教務課)までお知らせください。
※学生部メールアドレス:shogakukin@ad.ryukoku.ac.jp
1.龍谷大学給付奨学生(災害給付奨学生)/給付奨学金
■対象
本学に在学する学部生及び大学院生で、自然災害等により被害を受けた地域に本人又は父母のいずれか(又は生計維持者)が居住しており、学費支弁が困難であると認められ、かつ、奨学金申請書及び被災状況証明書等が提出できる方。
※災害救助法適用の有無にかかわらず、奨学生給付対象となる被害を受けた正規学生は全員申請可能です。
■金額
定める金額を上限とし、奨学委員会が決定します。
| 対象 |
奨学金額 |
| 父母のいずれか(又は生計維持者)が亡くなられた場合、又は、家屋が全壊(全焼)または大規模半壊した場合 |
年間授業料相当額 |
| 父母のいずれか(又は生計維持者)が負傷され、一ヶ月以上の加療が必要な場合、又は、家屋が半壊(半焼)若しくは床上浸水の場合 |
半期授業料相当額 |
休学している場合には在籍状況に応じた奨学金額を給付します。詳細は学生部(深草・瀬田)に問い合わせください。
2.龍谷大学親和会自然災害特別見舞金/保護者会組織によるお見舞い金
■対象
本学に在学する学部生及び大学院生で、自然災害等により被害を受けた地域に本人又は父母のいずれか(又は生計維持者)が居住して、被害を被り、かつ罹災証明書が提出できる方。
■金額
一律5万円(自宅全壊・親和会長が特に必要があると認めた場合、10万円を上限)
■その他
発給から1年以内の罹災証明書があるものを受付。
3.日本学生支援機構(緊急採用・応急採用)/貸与奨学金
■対象
本学に在学する学部生及び大学院生で自然災害による災害救助法適用地域に本人または父母のいずれか(または生計維持者)が居住する世帯で、当該の災害により家計が急変したことにより奨学金を希望される方。
※災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、災害救助法適用地域と同等の災害にあった世帯の学生ならびに同地域に勤務し、勤務先が被災した世帯の学生についても、上記に準じて取り扱う。
■貸与始期
| 緊急採用(第一種奨学金) |
入学年月を限度として、家計急変の事由が発生した月以降で申込者が希望する月。 |
| 応急採用(第二種奨学金) |
家計急変の事由が発生した月又は採用年度の4月以降で申込者が希望する月。
ただし、入学年月より前に遡って貸与を受けることはできません。 |
■貸与終期
| 緊急採用(第一種奨学金) |
修業年限の終期まで。 |
| 応急採用(第二種奨学金) |
修業年限の終期まで。 |
4.高等教育の修学支援新制度(家計急変採用)/給付奨学金
高等教育の修学支援新制度(給付奨学金・授業料等減免)は、給付奨学金と授業料等減免がセットになった国による支援制度です。
通常は、年に2回(4月・9月を予定)募集を行いますが、災害等を含む家計が急変した場合は、条件に該当する方については、事由発生後3か月以内に申込を行えば、随時出願が受け付けられます。
■対象となる家計急変の事由
A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故または病気により、半年以上、就労が困難
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職
ただし解雇など、非自発的失業の場合に限る。
D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当
①上記A~Cのいずれかに該当
②被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生
E:家庭内暴力から避難等した場合
■修学支援新制度 家計急変の概要
■採用にあたって要件
(1)家計基準
- 修学支援新制度の家計急変採用は、急変後の収入が修学支援新制度の家計基準を満たしていることが条件となります。
詳細は被災・家計急変時の給付奨学金の家計基準 | JASSOを参照してください。なお、ご自身が該当するかどうかは、日本学生支援機構の進学資金シミュレーターの「給付奨学金シミュレーション(保護者の方向け)をおおまかな目安としてご活用ください。最終的には日本学生支援機構にて判定を行います。
- また、家計基準には、資産基準があり、学生本人と生計維持者(2人)の資産額の合計が5,000万円未満(多子世帯の授業料等減免については3億円未満)である必要があります。
なお、資産とは現金やこれに準ずるもの(投資用資産として保有する金・銀等、預貯金、有価証券の合計額を指し、土地等の不動産は含みません)。なお、資産に関する証明書(預金通帳のコピー等)の提出は不要です。
(2)学力基準
修学支援の新制度については、家計急変採用であっても学力での審査があります。
詳細は、被災・家計急変時の給付奨学金の学力基準 | JASSOを参照してください。
また、採用となった場合には、適格認定という受給資格の継続が相応しいかの学業成績の判定が行われます。詳細は、適格認定(学業等) | JASSOを参照してください。
5.JASSO災害支援金について/給付奨学金
日本学生支援機構では、学生やその生計維持者・留学生の住居が、半分以上壊れたり、床上浸水したりするなどした場合など、一日でも早く元の生活に戻り、学業をつづけることができるよう、支援金(10万円)を支給しています(返す必要はありません)。
■申請の対象(以下の全てに該当する必要があります)
(1)本学大学、短期大学、大学院に在学中の方
※科目等履修生、研究生、聴講生等は除きます。
※JASSOの奨学金や他団体の経済的支援を受けていても申請することができます。
(2)自然災害や火災などにより、学生本人やその生計維持者が現に住んでいる家が、半壊(半流出・半埋没及び半焼失を含みます)以上の被害を受けたり、床上浸水となったり、自治体からの避難勧告等が1か月以上続いたりした方
※入学前・休学中に発生した災害は対象外です。
※同一の災害につき、申請は1回とします。
(3)学修に意欲があり、修業年限で学業を確実に修了できる見込みがある場合
※成績不振により留年中の方は除きます。ただし、成績自体に問題はなく、留学等のために同一学年を再履修している方は対象となります。
■申請方法
申請対象の方は、まずは学生部にご相談ください。
■JASSO災害支援金の概要
災害にあわれた学生・留学生への支援金(JASSO災害支援金)
■期限
2026年4月末までに学生部にご相談ください。
(※大学からJASSOへの申請期限は、災害がおきた日の次の月から数えて、6か月以内)