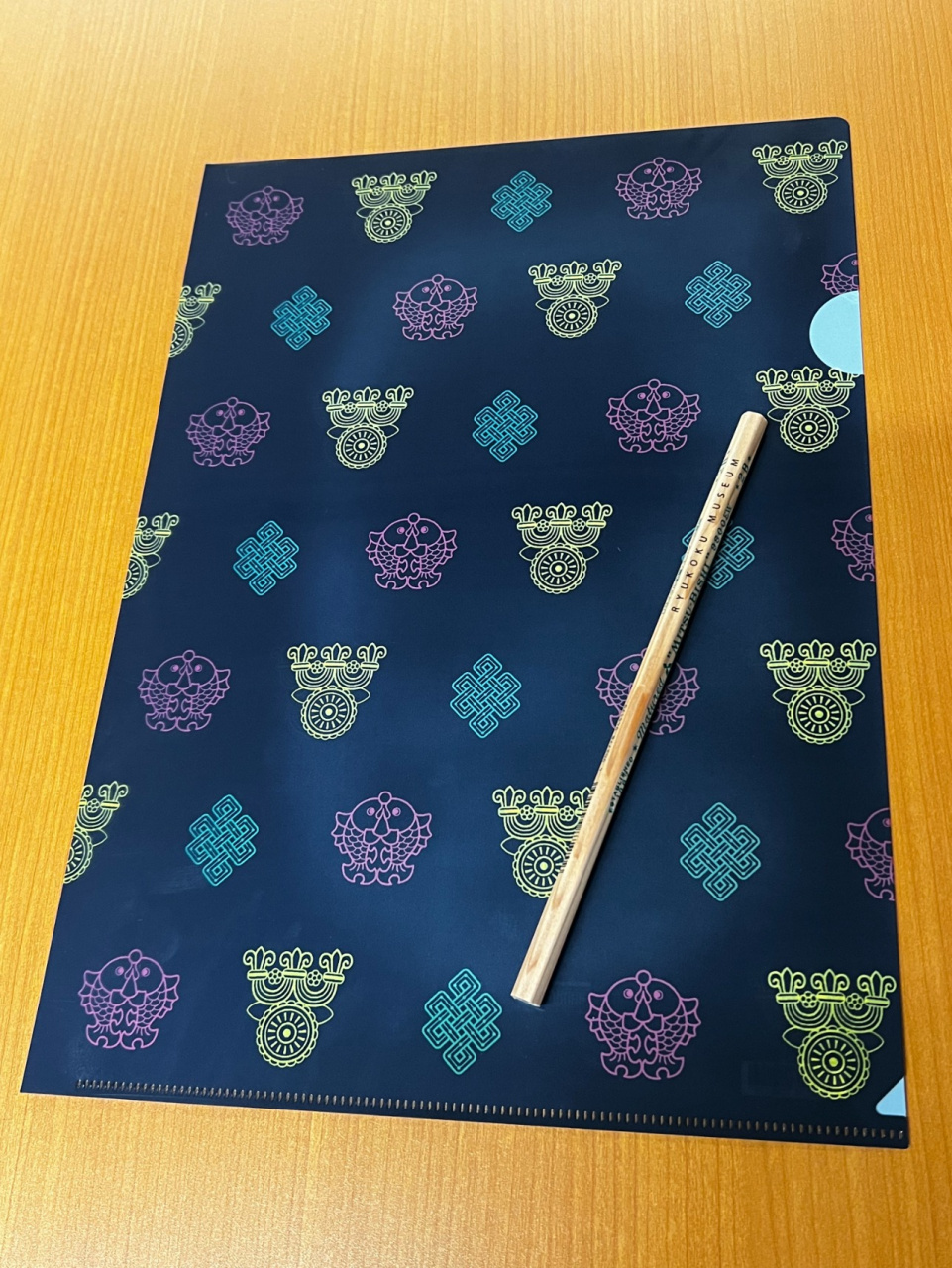「漁業体験 in 琵琶湖」を開催しました
2025年11月16日(日)早朝、滋賀県農政水産部水産課様との共催事業として、長浜市エリアの北湖にて、本学学生6名による「漁業体験 in 琵琶湖」を実施しました。
本事業は、漁業の後継者不足問題によりもたらされる、食料供給、地域経済、環境保全に関する社会課題に対し、自ら船に乗り、漁業を体験することで「琵琶湖」のこれからについて一緒に考えるために、産官学連携事業として企画しました。
漁業については、企画運営を株式会社フラン様、漁業を朝日漁業協同組合様にご協力いただき、竹生島周辺で「刺し網漁」を行い、たくさんのホンモロコとワカサギを収穫することができました。
予想を超える多数の応募者の中から抽選され、当日の早朝に初めて出会った学部も回生もバラバラな学生同士が船の上で協力し合い、網にかかった魚を楽しみながら外していました。
参加者からは「湖魚に関する知見を深めることができた」、「自然を相手する仕事の大変さを肌で感じることができた」、「漁師さんにリスペクトの気持ちを持つようになった」、「手の中に魚の命を感じた」などの声があり、大変有意義な体験となりました。
最後に組合長より、獲れたてのホンモロコとワカサギの塩焼きを作っていただき、非常に美味しくいただきました。
11月下旬には本学瀬田キャンパス不二家食堂にて、「湖魚食材消費応援事業」として、湖魚であるコアユとワカサギの天ぷらが期間限定メニューとして提供する予定です。是非ご利用ください。
「湖魚食材消費応援事業」
主催:滋賀県 農政水産部 水産課 企画運営:株式会社フラン
協力:龍谷大学龍谷エクステンションセンター、株式会社不二家商事
滋賀県漁業協同組合連合会
龍谷大学は、これからも産官学金連携を通じて、社会課題の解決に貢献します。