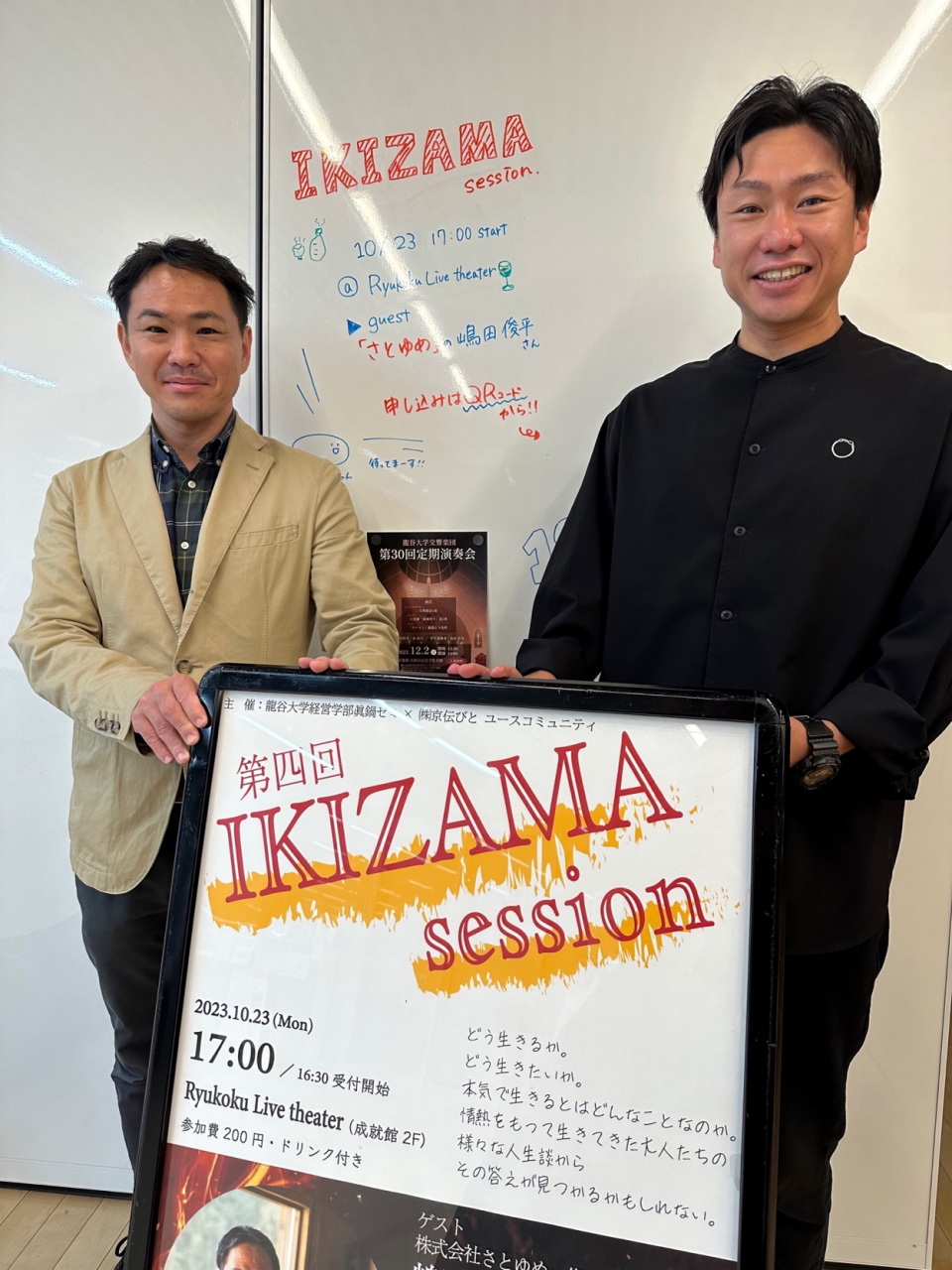マルコメ株式会社の甘酒を食品栄養学科の学生へ配布しました!
2023年11月 食品栄養学科の学生へ授業内で、マルコメ株式会社の糀甘酒を配布しました。
今回の配布は、2021年に製品開発プロジェクトでマルコメ株式会社にご協力いただいた繋がりから始まり、マルコメ株式会社に農学部の卒業生(21年卒)が在籍していることもあり実現しました。食品栄養学科の学生へ配布を行ったのは、管理栄養士を目指す食品栄養学科の学生に糀甘酒の栄養成分などを学んでもらうことで、調理などに活用してほしいという思いが込められています。
幕末から親しまれてきた糀甘酒には、疲労回復効果や美肌効果、整腸作用効果があると言われています。アルコール0%で砂糖不使用など非常に栄養成分が高いのが特徴です。その糀甘酒を実際に試飲した学生たちは、味わいながらどんな料理に合うかなどを話し合っていました。
【学生の感想】
・甘味が強く美味しく、飲みやすかったです。少し酸味を加えてカルピスやヤクルトなどに近づけるのもよいと感じました。
・甘酒は普段あまり飲まないですが、そこまで甘酒独特の香りがせず、飲みやすかったです。
・知っている味のような気がしたのですが、何の味か分からない不思議な味でした。
・はちみつみたいな甘さがあるので、ハニーミルクティーにしてもよさそうだと思いました。冷たくするか、暖かくして飲むのも面白いと思いました。
・以前、マルコメさんの甘酒(プラス糀 糀甘酒)を飲んだことがあるのですが、その商品よりも酒粕特有の風味が少なく、甘酒が苦手な私でも飲みやすいと感じました。
・人によって好みは変わると思いますが、味が濃くて比較的飲みやすかったです。お酒を飲んでいるという感覚は全くありませんでした。