ブラウザからレイアウト自由自在
Layout Module
ここにメッセージを入れることができます。

2023(令和5)年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害で被災した学生への各種奨学金等のお知らせ
2023(令和5)年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害で被災され...

2023年8月8日、9日に、社会福祉士国家資格取得支援のための社会福祉士...

【社会福祉学科】多文化背景の人が多く住む「東九条」についての特別講義を実施
多文化共生をめざし東九条で支援を行うNPO法人東九条まちづくりサポー...
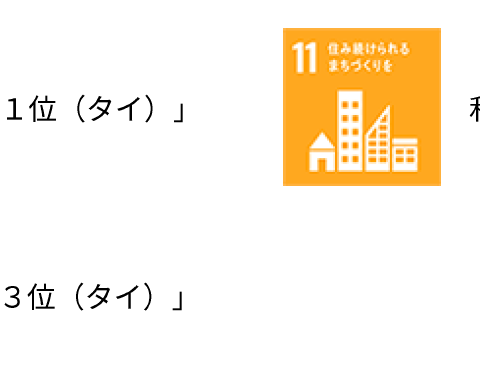
SDGsに対応した「THEインパクトランキング2023」で私大5位、西日本私大2位
6月1日、英国の教育専門誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーション(THE)...

大津市提携 龍谷講座 令和5年度「おおつ学」大津人基礎講座(2)
大津市大石龍門。六万三千坪の自然豊かな丘陵地に、叶 匠壽庵の本社と工...

大学生活で、性的指向や性自認など、性に関する悩みや困っていることに...
バドミントン日本代表B代表の西大輝選手(政策学部3年・スポーツサイエンスコース・本学バドミントン部所属)・佐藤灯選手(2023年3月卒・ACT SAIKYO所属)ペアが10月17日~22日に開催された「インドネシアインターナショナルチャレンジ2023」に出場し、国際大会優勝を果たしました。国際大会の優勝は3大会連続です。
A代表入りを目指す、西・佐藤ペアへの引き続きのご声援、よろしくお願いいたします。
<本学バドミントン部Instagram>
https://www.instagram.com/ryukoku_bad/
◆びわ湖の日滋賀県提携 公開講座
「琵琶湖と私たちの暮らし」
<第3回>
日 時:2023年11月18日(土)13:30~15:00
場 所:龍谷大学 大阪梅田キャンパス
講 師:持田 由希子(東洋紡株式会社 サステナビリティ推進部長)
安川 政宏(東洋紡エムシー株式会社 環境ソリューション開発セクションアクア膜基礎開発グループリーダー)
テーマ:化学メーカーのサステナビリティ取り組みと環境保全に貢献する独自の技術
「化学メーカーにおけるサステナビリティの取り組み紹介とグループを代表する製品:中空糸幕が提供する社会的価値~安全な飲料水と持続可能エネルギー」
びわ湖100地点環境DNA調査の結果を紹介します(講座に引き続き開催 14:30~15:00)
「びわ湖の日チャレンジ!みんなで水を汲んでどんな魚がいるか調べよう!」
山中 裕樹(龍谷大学生物多様性科学研究センター長・先端理工学部 准教授)
開催方法:対面とオンライン(Zoomウェビナー)のハイブリッド開催
定 員:30名(対面)+100名(オンライン)【先着順、受講無料】
※Peatixからのお申込みになります。以下のURLからお申込みください。
対面参加の申込みはこちらから
https://biwakonohi-ryukoku3-taimen.peatix.com
オンライン参加の申込みはこちらから
https://biwakonohi-ryukoku3-online.peatix.com
【本件のポイント】

龍谷大学農学部の白味噌を使用した洛空オリジナルメニュー

学生とホテルのシェフが提供メニューの試作を作っている様子
【本件の概要】
龍谷大学農学部と(株)石野味噌、ウェスティン都ホテル京都が連携し、白味噌を使用したメニューを開発し、ウェスティン都ホテル京都で11月から開催する「京都の味覚ブッフェ」で提供されます。
メニュー開発に使用した白味噌は農学部と創業240年の歴史をもつ京都の老舗味噌蔵(株)石野味噌が連携して開発しました。原材料には、農学部と農事組合法人ふぁーむ牧が収穫した国産大豆「ことゆたか」と近江米を使用し、(株)石野味噌が配合したもので、農学部の持続可能な食の循環を考え、地域に貢献できる研究・教育を目指す取組として、開発した商品です。
メニュー開発を行った学生たちは、普段は学校や病院などの給食施設における適切な栄養管理を行いかつ衛生面で安心・安全な食事提供について研究を行ってます。今回は、高級ホテルで提供する白味噌を使用したメニュー作りという、今までとは異なるアプローチでの挑戦となりました。8人の学生が農学部で学んだ知見を活かして思い思いに試作し、ウェスティン都ホテル京都の一流シェフの審査を経て、和食・洋食・デザートで一品ずつ採用されました。採用メニューが決定したあとは、ホテルでシェフと試行錯誤しながら試作を重ねてブラッシュアップし、この度完成しました。
■採用されたメニュー
<和食>鴨ロースとえび芋の白味噌仕立て柚子風味 考案者:食品栄養学科4年 西島 美帆 さん

【学生コメント】
白味噌のとろみ調節をすることが難しかったです。シェフに片栗粉を使わなくてもちょうど良いとろみをつける方法を教えてもらい勉強になりました。
【担当シェフコメント】
鴨ロースのソテーと焼きねぎの相性も良く、龍大白味噌をダイレクトに味わえる盛り付けも良かったです。柚子で風味をプラスし、海老芋のから揚げを添えることでボリュームと京都らしさを演出しました。
<洋食>丹波しめじを使った豆乳・白味噌パスタ 考案者:食品栄養学科4年 佐藤 楓 さん

【学生コメント】
京都の食材である丹波しめじ、豆乳、白味噌を使用し、食材から秋と京都を感じられるような料理になったと思います。また、トマトを使用することで、重たくなりすぎずまとまりが出るように気を配りました。
【担当シェフコメント】
丹波しめじ、豆乳、白味噌とどれも京都を連想する食材で、お客様にわかりやすいメニューだと思います。豆乳を使うことで白味噌の風味が損なわれずに仕上がっていて、トマトの酸味が加わることで全体のバランスが良くなり完成度の高い仕上がりになりました。
<デザート>白味噌を使用したさつまいもチーズケーキ 考案者:食品栄養学科4年 比嘉 真歩 さん

【学生コメント】
旬のさつまいもが持つ自然な甘さを引き立てるためにチーズケーキに白味噌を隠し味として入れています。白味噌を主役にしたアングレーズソースやさつまいもアイスと一緒に様々な食べ方で楽しんでほしいです。
デザートと白味噌を調和させることは難しく感じられましたが、幾度も試作を重ね贅沢で濃厚な味わいのチーズケーキが仕上がりました。是非ご賞味下さい。
【担当シェフコメント】
デザートに白味噌を使用するのは難しかったと思いますが、秋の味覚を代表するさつまいもとチーズケーキの組み合わせはとても良かったです。白味噌のアングレーズソースを別添えにする事で程よい甘みと塩味の調和のとれた一皿に仕上がりました。

学生とホテルのシェフが提供メニューの試作を作っている様子
【指導教員:朝見祐也教授コメント】
このたびは学生たちにとってやりがいのある事業の提案をいただき、大変ありがたく思っています。
和食、洋食そしてデザートのそれぞれの第一線で活躍するシェフから料理・調理の指導をいただきながらメニューを開発するというのは大変貴重な経験でありました。学生たちが何度も試作をして作り上げたメニューを多くの方にお召し上がりいただきたいと思います。
■実施期間および店舗
1. 学生のメニューが提供される期間:11月1日(水)~11月30日(木)
2. 実施店舗:ウェスティン都ホテル京都2階 オールデイダイニング「洛空」
3. 営業時間:ランチ11:30~14:30/ディナー17:00~21:00
※ランチ・ディナー共に土・日・祝日は30分延長
(詳細)https://www.miyakohotels.ne.jp/westinkyoto/restaurant/raku/menu/25867/
【ウェスティン都ホテル京都 オールデイダイニング「洛空」】
東山の豊かな自然と京都市街の景色がお楽しみいただけるブッフェレストラン。ライブキッチンでお届けする出来立てメニューを中心に、京都近郊の漁港からの魚介や京野菜を使った多彩な料理など季節ごとのプロモーションを提供している。
■これまでの取り組みの流れ
4月10日 キックオフミーティング
4月28日 ウェスティン都ホテル京都を視察し、シェフから指導を受ける
5月 食品栄養学科、大学院農学研究科の8名の学生がメニュー試作準備を進める
6月 9日 ウェスティン都ホテル京都のシェフによる審査会を実施し、和食・洋食・デザートの採用メニューが決定
7月~9月 メニューを採用された学生とシェフでホテルで提供する料理の試作を重ねる。

問い合わせ先:龍谷大学 農学部教務課 <担当:蘆田>
Tel 077-599-5601 agr@ad.ryukoku.ac.jp https://www.agr.ryukoku.ac.jp/
【本件のポイント】
• 農学部食品栄養学科、農学研究科の給食経営管理学研究室(朝見祐也教授)に所属する学生が、龍谷大学が販売している白味噌を使った和食・洋食・デザートのメニューを考案。
• 学生が考案したメニューをベースに学生とホテルのシェフが検討を重ね、ブラッシュアップし、ホテルで提供することが決定。
• 高級ホテルのシェフから指導により、普段の活動では得られない知見を得る機会に。
【本件の概要】
龍谷大学農学部と(株)石野味噌、ウェスティン都ホテル京都が連携し、白味噌を使用したメニューを開発し、ウェスティン都ホテル京都で11月から開催する「京都の味覚ビュッフェ」で提供されます。
メニュー開発に使用した白味噌は農学部と創業240年の歴史をもつ京都の老舗味噌蔵(株)石野味噌が連携して開発しました。原材料には、農学部と農事組合法人ふぁーむ牧が収穫した国産大豆「ことゆたか」と近江米を使用し、(株)石野味噌が配合したもので、農学部の持続可能な食の循環を考え、地域に貢献できる研究・教育を目指す取り組みとして、開発した商品です。
メニュー開発を行った学生たちは、普段は学校や病院などの給食施設における適切な栄養管理を行いかつ衛生面で安心・安全な食事提供について研究を行ってます。今回は、高級ホテルで提供する白味噌を使用したメニュー作りという、今までとは異なるアプローチでの挑戦となりました。8人の学生が農学部で学んだ知見を活かして思い思い試作し、ウェスティン都ホテル京都の一流シェフの審査を経て、和食・洋食・デザートで一品ずつ採用されました。採用メニューが決定したあとは、ホテルでシェフと試行錯誤しながら試作を重ねてブラッシュアップし、この度完成しました。
■採用されたメニュー
<和食>鴨ロースとえび芋の白味噌仕立て柚子風味
考案者:食品栄養学科4年 西島 美帆 さん
【学生コメント】
白味噌のとろみ調節をすることが難しかったです。シェフに片栗粉を使わなくてもちょうど良いとろみをつける方法を教えてもらい勉強になりました。
【担当シェフコメント】
鴨ロースのソテーと焼きねぎの相性も良く、龍大白味噌をダイレクトに味わえる盛り付けも良かったです。柚子で風味をプラスし、海老芋のから揚げを添えることでボリュームと京都らしさを演出しました。
<洋食>丹波しめじを使った豆乳・白味噌パスタ
考案者:食品栄養学科4年 佐藤 楓 さん
【学生コメント】
京都の食材である丹波しめじ、豆乳、白味噌を使用し、食材から秋と京都を感じられるような料理になったと思います。また、トマトを使用することで、重たくなりすぎずまとまりが出るように気を配りました。
【担当シェフコメント】
丹波しめじ、豆乳、白味噌とどれも京都を連想する食材で、お客様にわかりやすいメニューだと思います。豆乳を使うことで白味噌の風味が損なわずに仕上がっていて、トマトの酸味が加わることで全体のバランスが良くなり完成度の高い仕上がりになりました。
<デザート>白味噌を使用したさつまいもチーズケーキ
考案者:食品栄養学科4年 比嘉 真歩 さん
【学生コメント】
旬のさつまいもが持つ自然な甘さを引き立てるためにチーズケーキに入っている白味噌を隠し味として入れています。白味噌を主役にしたアングレーズソースやさつまいもアイスと一緒に様々な食べ方で楽しんでほしいです。デザートと白味噌を調和させることは難しく感じられましたが、幾度も試作を重ね贅沢で濃厚な味わいのチーズケーキが仕上がりました。是非ご賞味下さい。
【担当シェフコメント】
デザートに白味噌を使用するのは難しかったと思いますが、秋の味覚を代表するさつまいもとチーズケーキの組み合わせはとても良かったです。白味噌のアングレーズソースを別添えにする事で程よい甘みと塩味の調和のとれた一皿に仕上がりました。
【指導教員:朝見祐也教授コメント】
このたびは学生たちにとってやりがいのある事業の提案をいただき、大変ありがたく思っています。和食、洋食そしてデザートのそれぞれの第一線で活躍するシェフから料理・調理の指導をいただきながらメニューを開発するというのは大変貴重な経験でありました。学生たちが何度も試作をして作り上げたメニューを多くの方にお召し上がりいただきたいと思います。
■実施期間および店舗
1. 学生のメニューが提供される期間:11月1日(水)~11月30日(木)
2. 実施店舗:ウェスティン都ホテル京都2階 オールデイダイニング「洛空」
3. 営業時間:ランチ11:30~14:30/ディナー17:00~21:00
※ランチ・ディナー共に土・日・祝日は30分延長
(詳細)https://www.miyakohotels.ne.jp/westinkyoto/restaurant/raku/menu/25867/
【ウェスティン都ホテル京都 オールデイダイニング「洛空」】
東山の豊かな自然と京都市街の景色がお楽しみいただけるブッフェレストラン。ライブキッチンでお届けする出来立てメニューを中心に、京都近郊の漁港からの魚介や京野菜を使った多彩な料理など季節ごとのプロモーションを提供している。
■これまでの取り組みの流れ
4月10日 キックオフミーティング
4月28日 ウェスティン都ホテル京都を視察し、シェフから指導を受ける
5月 食品栄養学科、大学院農学研究科の8名の学生がメニュー試作準備進める
6月 9日 ウェスティン都ホテル京都のシェフによる審査会を実施し、
和食・洋食・デザートの採用メニューが決定
7月~9月 メニューを採用された学生とシェフでホテルで提供する料理の試作を
重ねる。



