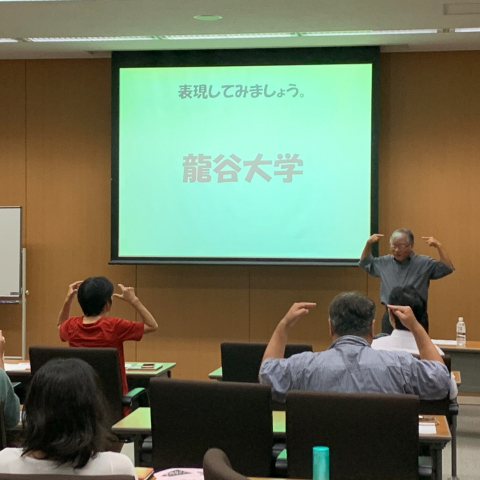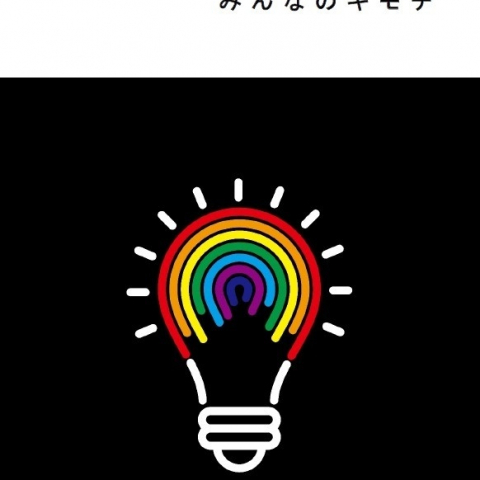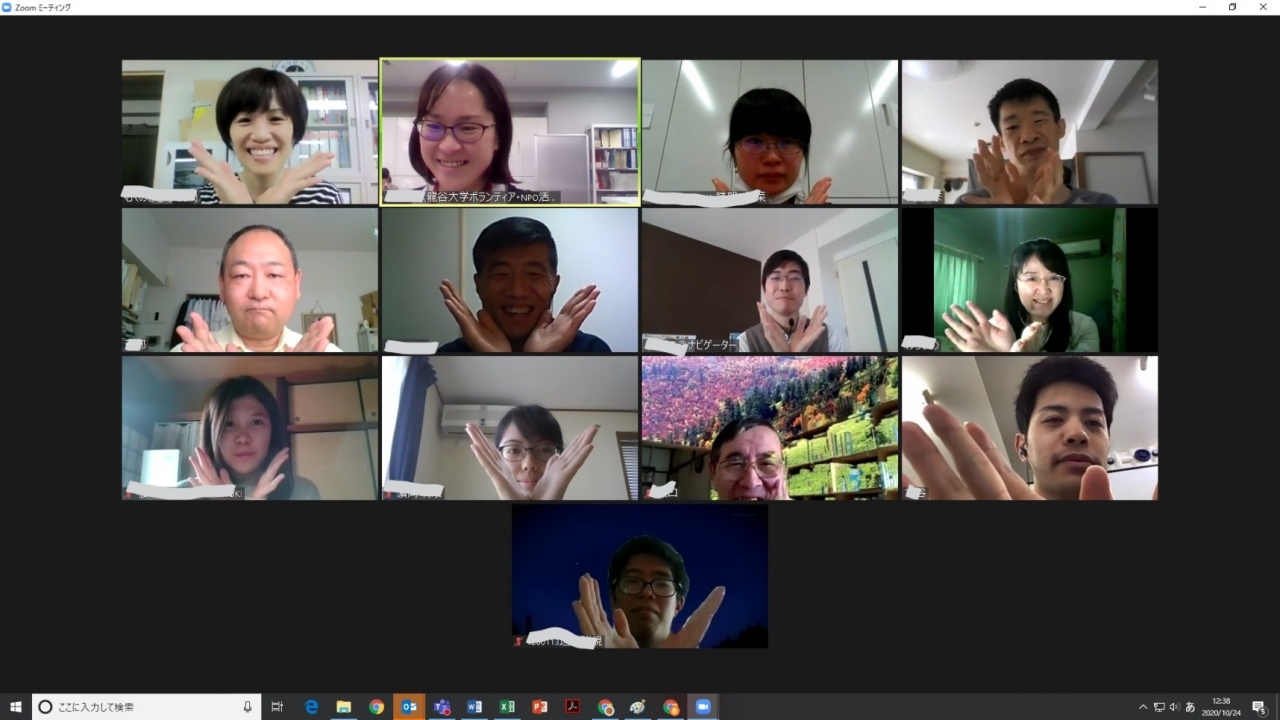龍谷ミュージアム 企画展「ほとけと神々大集合-岡山・宗教美術の名宝-」プレス内覧会のお知らせ 11月20日(金)10:30 ~
【本件のポイント】
・岡山県立博物館の改修工事に合わせ、同館が所蔵・寄託する宗教美術品約100件を龍谷ミュージアムが受託。
・これら多彩な宗教美術の中から「密教」と「神仏習合」にかかわる名宝約50件を展示。
・長福寺(美作市)の「十二天像」、高野神社(津山市)の「木造 獅子」をはじめ重要文化財が11件。
・岡山龍谷高等学校(龍谷総合学園加盟校)の生徒達が、寺社への取材に基づき紹介するパネルをエントランスに展示。
<プレス内覧会>
① 日時:11月20日(金) 10:30 ~12:00 (受付 10:00 ~)
② 場所:龍谷ミュージアム 1階101講義室
<プレス内覧会内容>
① 展覧会の概要説明
② 展示室内における主な展示品解説(写真撮影可)
③ 質疑応答
<展覧会の概要>
1.名 称 企画展「ほとけと神々大集合-岡山・宗教美術の名宝-」
2.会 期 2020年11月21日(土)~ 12月27日(日)、2021年1月6日(水)~1月24日(日)
3.休 館 日 月曜日(ただし、11月23日、1月11日は開館)、11月24日(火)
4.開館時間 10:00~17:00(入館は16:30まで)
5.会 場 龍谷ミュージアム
〒600-8399 京都市下京区堀川通正面下る(西本願寺前)
6.主 催 龍谷大学 龍谷ミュージアム、朝日新聞社、京都新聞
7.入 館 料 一般900(700)円、高大生500(300)円、小中生200(100)円
※( )内は20名以上の団体料金
※小学生未満、障がい者手帳等の交付を受けている方およびその介護者1名は無料
※原則として、全てのお客様に龍谷ミュージアムHPからオンラインで事前予約をお願いしています。事前予約なしにお越しになられた際は、お待ちいただくことがあります。
※事前予約や、新型コロナウイルス感染対策に関するお願い等、最新情報は龍谷ミュージアムHPをご確認ください。
https://museum.ryukoku.ac.jp/
※新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては、臨時休館することがあります。
問い合わせ先 : 龍谷ミュージアム
Tel.075-351-2500 Fax.075-351-2577
E-mail ryumuse@ad.ryukoku.ac.jp