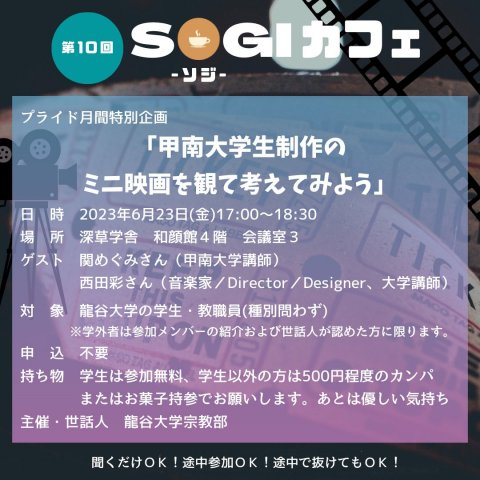本学卒業生ベンチャー企業RE-SOCIALが「KYOTONEXTAWARD2023」最優秀賞を受賞【REC事務部】
京都府・京都市・京都商工会議所で組織する京都ブランド推進連絡講義会では、今年度から次代の京都ブランドとなり得る新たな担い手を発掘・表彰する「KYOTO Next Award」を設けました。10月16日(月)に開催された、その記念すべき第1回の表彰式にて、本学卒業生が立ち上げたベンチャー企業「株式会社RE-SOCIAL」が最優秀賞を受賞しました。
主な選定理由として、鹿肉の解体や発送に至る技術面、鹿肉だけでなく内臓や骨、皮など多くの部位を有効活用しようとする商品や事業戦略、ジビエ市場で着実に売り上げを伸ばし、獣害被害解決と地域への貢献がなされていることや、同社の「いのちをいただく」といった姿勢が挙げられました。
RE-SOCIALは、政策学部卒業生 笠井 大輝さん、江口 和さん、山本 海都さんが在学中に立ち上げた企業で、獣害の対策として駆除された鹿や猪がそのまま廃棄されている現状を目にしたことが起業のきっかけとなりました。2020年10月に京都府笠置町で「京都鹿肉専門やまとある工房」を開業し、「自然に敬意と感謝の気持ちを忘れず、本来あるべき人間と自然の関係性・命への感謝を、『食』を通して伝えていきたい。」という思いから、野生鹿の生け捕りから養鹿、生体搬送、活け締め、解体処理、販売までを一貫して行っています。
同社は2023年6月に京都市南区に飲食店「NATURAL BAL MEAT UP」もオープンし、ジビエ料理の普及に奮闘されています。
【会社名】株式会社RE-SOCIAL
【所在地】京都府笠置町大字有市
【URL】https://www.resocial-kasagi.com/
【飲食店】NATURAL BAL MEAT UP
【所在地】京都府京都市南区東九条西岩本町16-3
【開 店】17:00~22:00
【定休日】月曜日