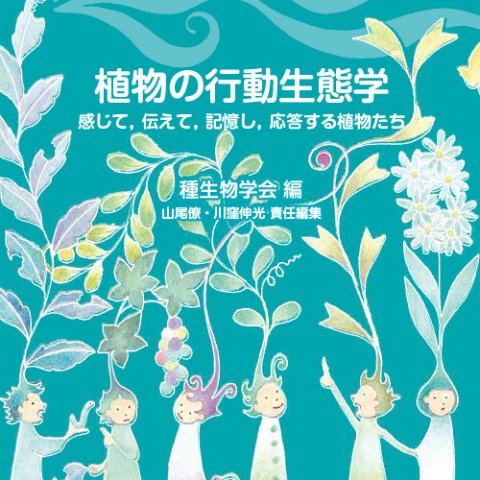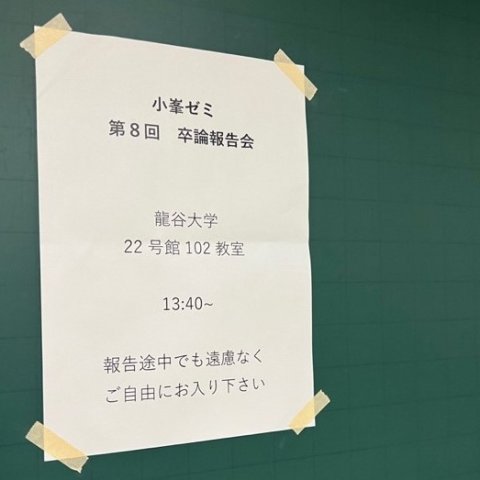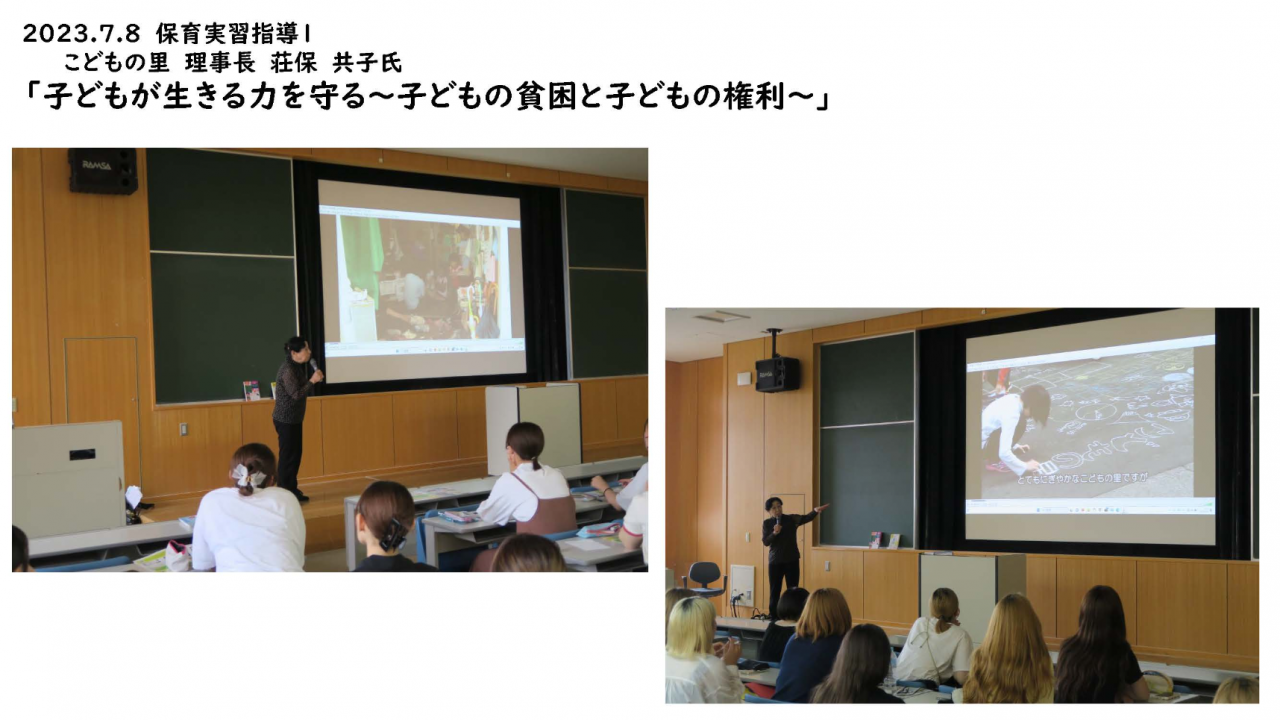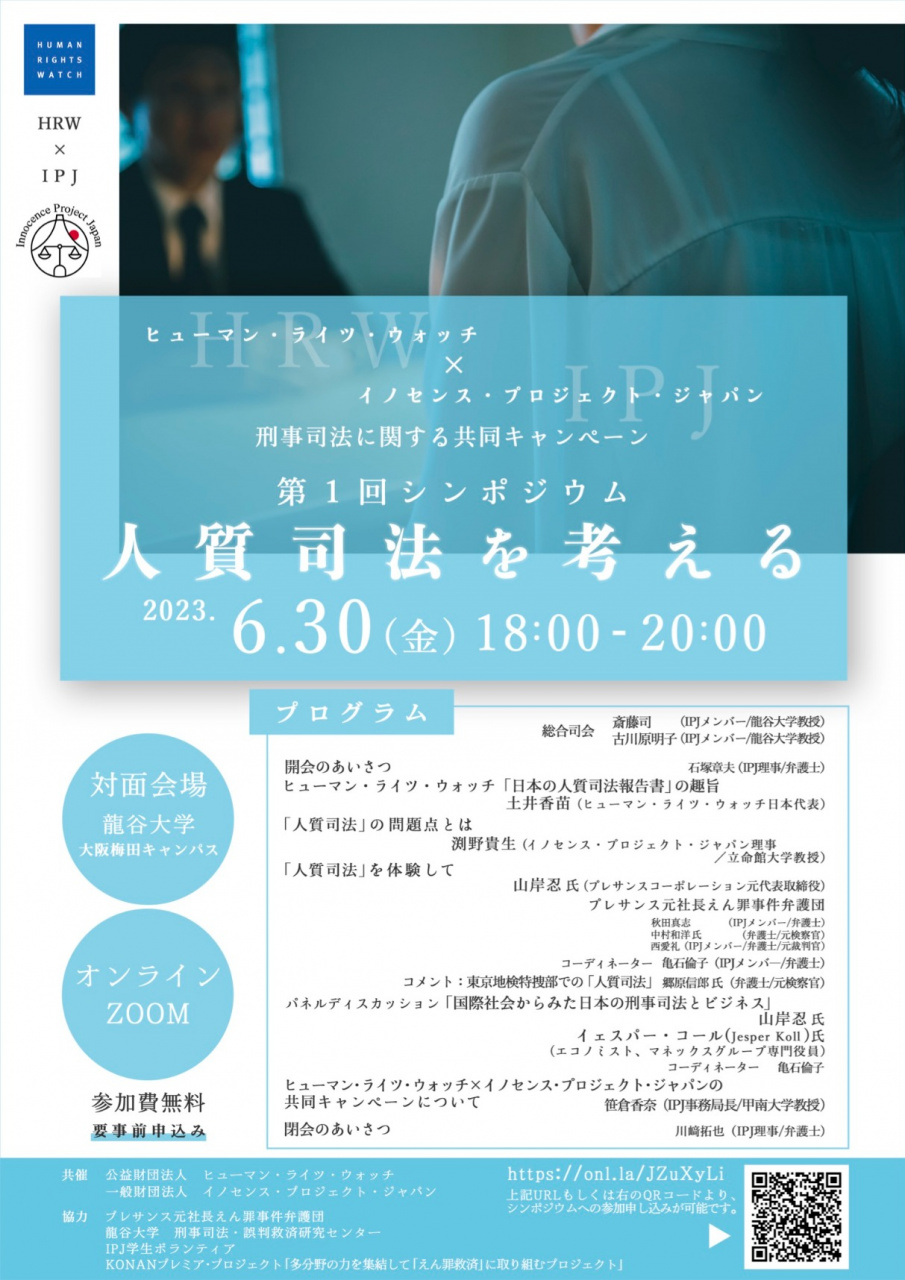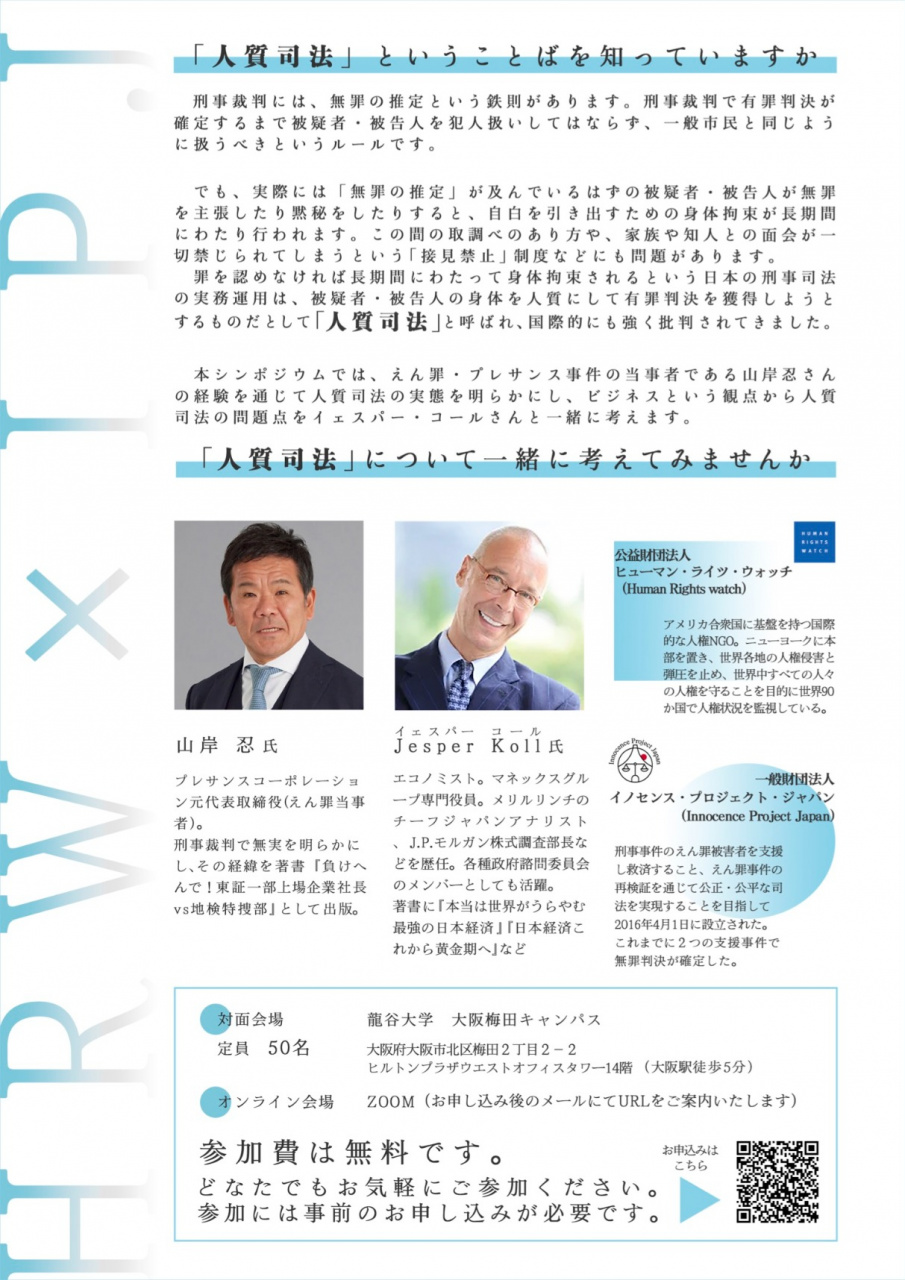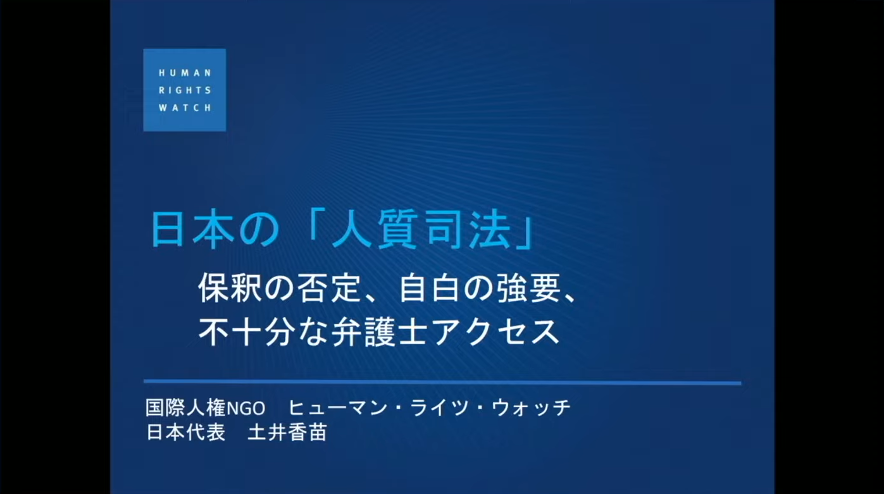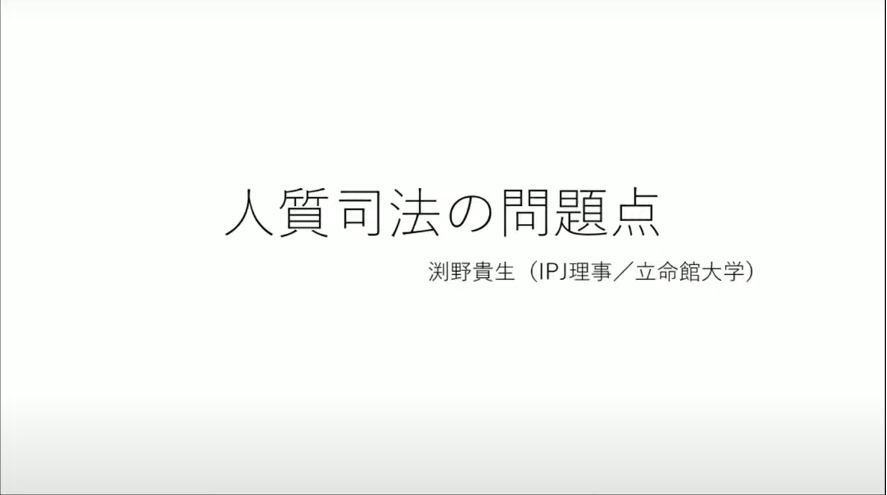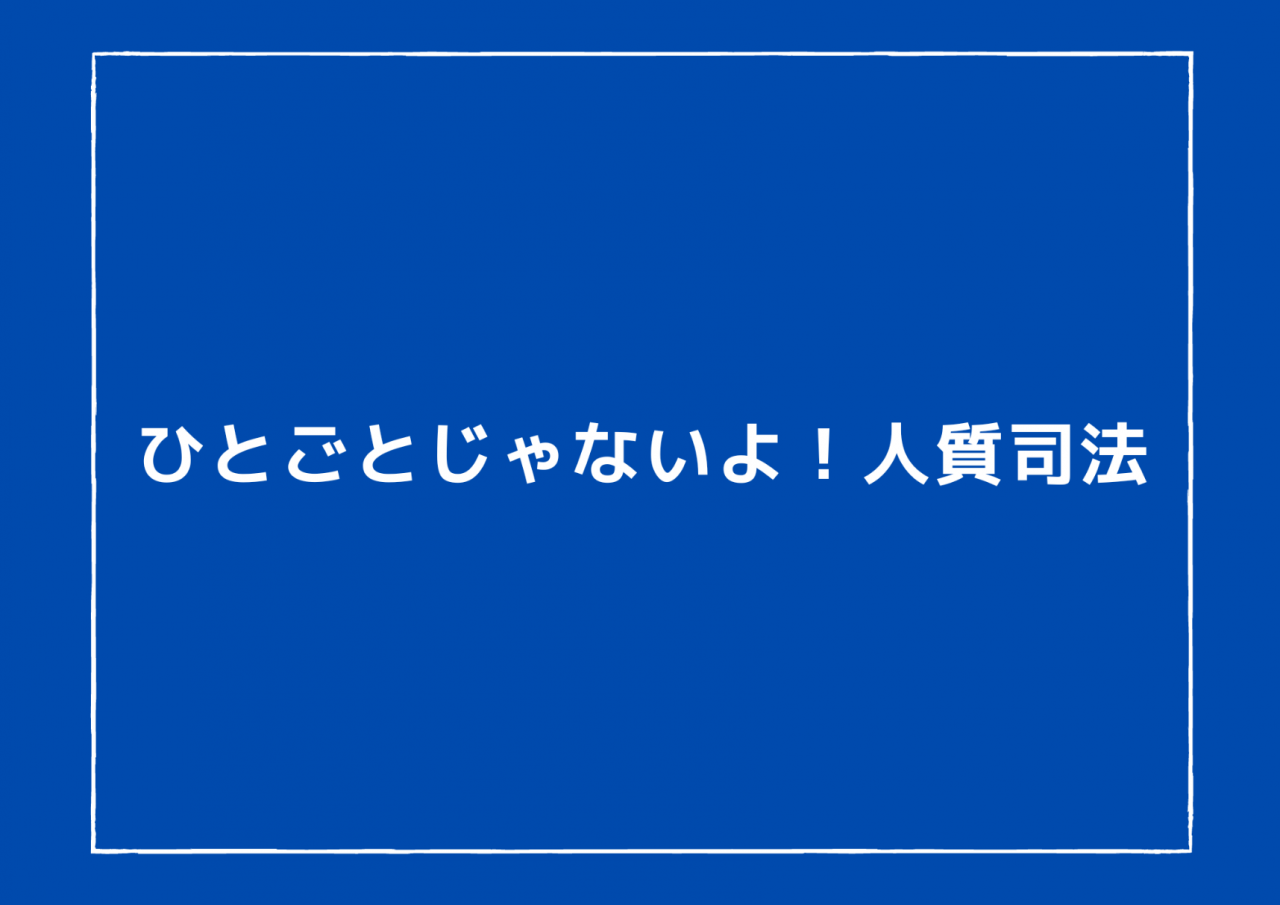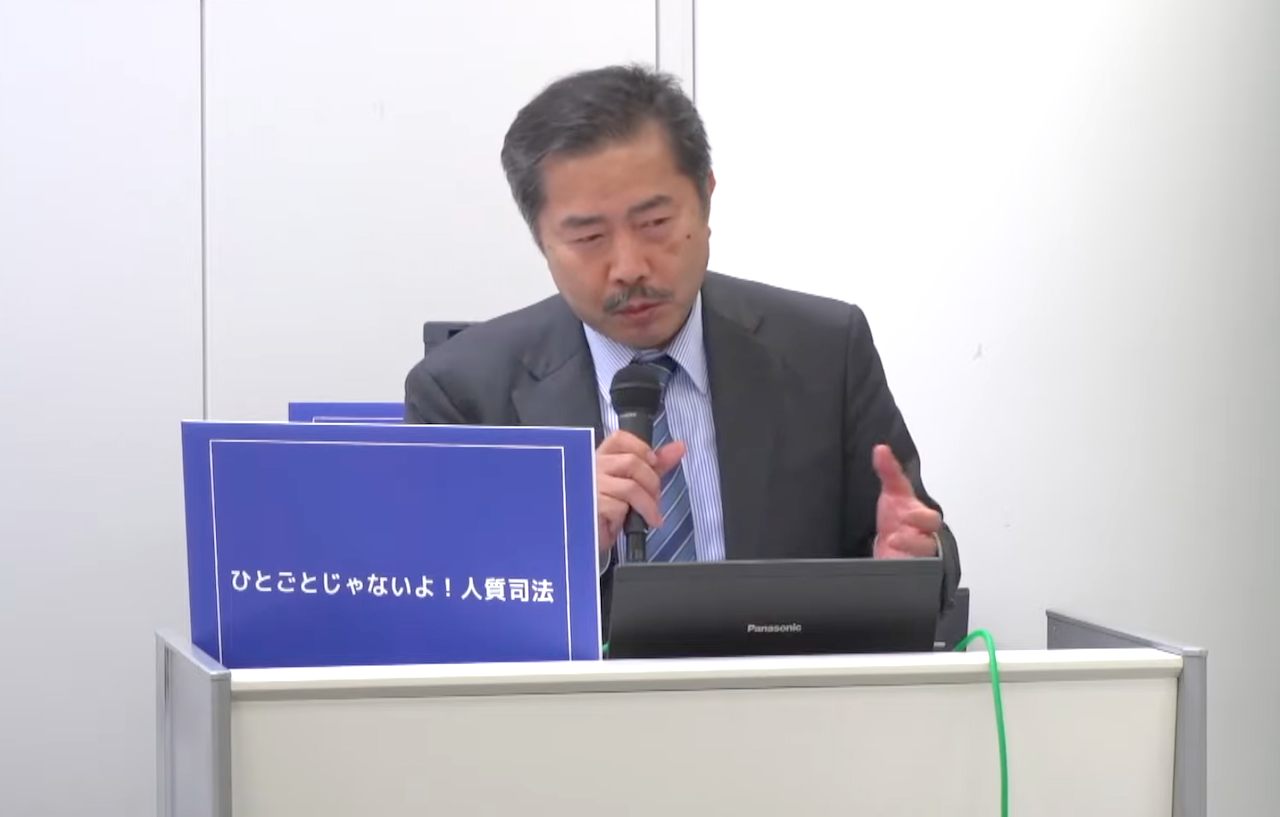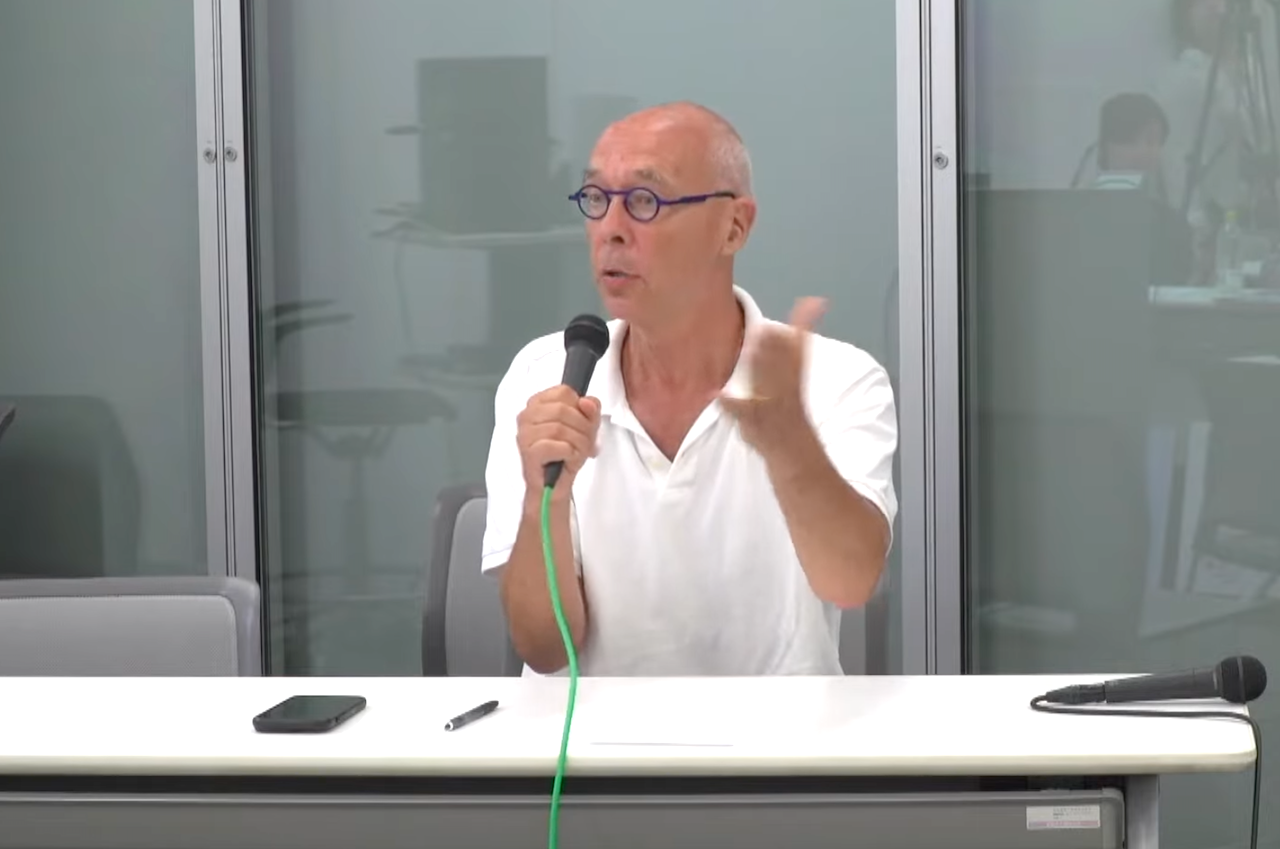【短期大学部】2023年度 「アカデミック・スカラシップ奨学生(在学採用型)」・「学部教育賞」授与式を行いました
本学では、学業成績・人物が特に優秀な学生を対象に「アカデミック・スカラシップ奨学生(在学採用型)」の制度を設けています。
2023年度は、社会福祉学科2名、こども教育学科4名の学生が採用され、この度、表彰状授与式を行いました。表彰式では、黒川雅代子・短期大学部長から表彰状が手渡されました。
また、「親和会優秀者表彰制度」として、「学部教育賞」の授与も行いました。この表彰制度は、学業において著しい成績・成果をおさめた個人・ゼミに対し、学生が意欲的に自らの目標に向かって自己研鑽することを奨励する制度として、創設されたものです。
表彰式では、黒川雅代子・短期大学部長から表彰状と副賞が手渡されました。
表彰された学生には、今後も、他の学生の模範となるよう、勉学により一層励んでいただきたいと思います。