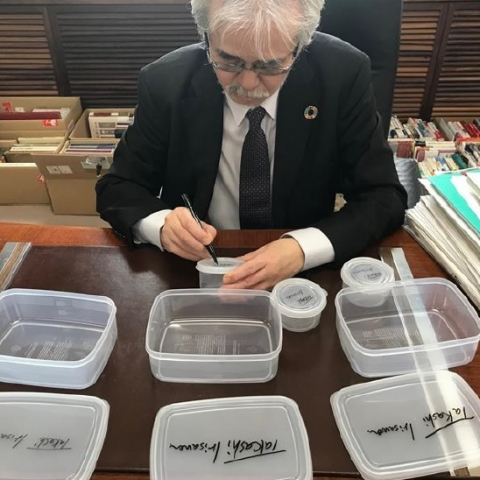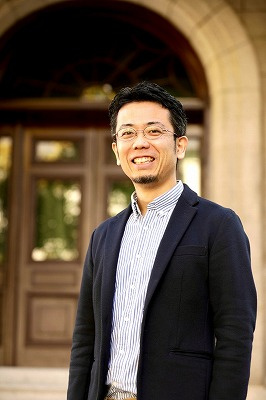コミュニティマネジメント実習「伏見まちづくり」プロジェクトで「はなやまっち」を制作・展示
龍谷大学社会学部のコミュニティマネジメント実習(担当:坂本清彦特任准教授)「京都伏見まちづくり」プロジェクトの一環で、京都市伏見区の納屋町商店街の公式キャラクター「なやまっち」を、伏見区内産の花を使って制作し、瀬田学舎内に展示しました。
「はなやまっち」と名付けた本企画は、新型コロナウイルス感染対策で学外での実習活動が中断されている中、受講生が少しでも伏見のことを学び、伏見への想いを伝えるために行なったものです。

高矢農園さんのジニア
花でつくる「はなやまっち」の制作にあたっては、昔から花の産地である伏見の地元産の花を使うことにしました。伏見区南部・向島で花苗を生産する高矢農園さんに、黄色と赤のジニア(百日草)の苗を準備していただき、「はなやまっち」をその2つの色を使い、制作することになりました。
受講生たちは、花でどう「はなやまっち」を表現するか1からアイデアを出しあいました。スチール棚用の部材と育苗用トレーで組んだ枠に、花を「なやまっち」の形にならべ、「なやまっち」の特徴的な目、まゆ、口などは、プラスチックシートを使い、フェルトで「納屋町」の文字を書いた前掛けなども手作りしました。
受講生からは、「何もかも1からで、何から始めたらいいのかわからなかったけれど、先生の支えやメンバーとのチームワークでアイデアも出せて構造も決まられた」「制作にあたっても、暑い中での作業で大変でしたが、部品を組み立てる役と顔のパーツなどを作る役とでわかれ、一人一人が自分の役割作業に熱心に取り組み完成させることができました」といった感想が出されました。
制作から1週間経過し花が増え「なやまっち」らしくなった段階で、瀬田学舎で「はなやまっち」を展示しました。「はなやまっち」は、納屋町商店街のSNSなどでも紹介してもらいました。1週間にわたる展示の結果、多くの方々に伏見、商店街、学生たちの取り組みを知ってもらえればと考えています。
なお、はなやまっちの制作にあたっては、納屋町商店街はじめ、京都市東部農業振興センター、瀬田学舎の植栽を管理されている守山市の造園業者宝山園さん、そして龍谷大学瀬田学舎のスタッフの方々にも大変お世話になりました。ありがとうございました。