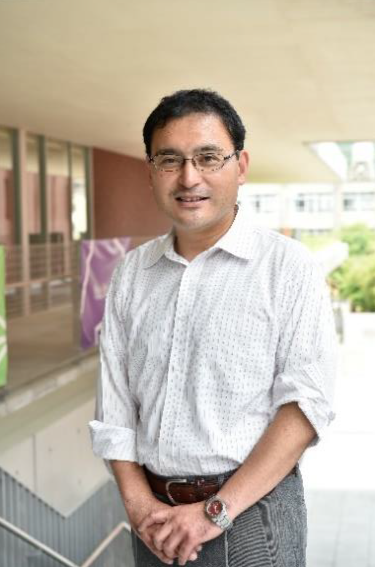パソコン・ノートテイカー交流会を開催しました【文学部】
12月17日(火)に文学部で勤務しているパソコン・ノートテイカーの交流会を開催し、情報共有や交流を行いました。
ノートテイカーはいわば“音の同時通訳”です。講義や学生による発表など授業中の音声情報を文字にして、聴覚障がいのある学生に伝えるものです。
文学部では次年度に向けて、4月から大宮学舎で勤務できるノートテイカー(学生アルバイト/1コマ=90分1,500円)を募集しています。
テイカーは2名で協力して勤務します。養成講座も実施いたしますので、初心者でも安心して応募していただけます。
就職活動や教育実習、卒論の準備や体調不良等で休む場合は教務課で交代のテイカーを手配しますので、可能な範囲で、1コマでも協力していただける方の応募をお待ちしています。(定期試験中の勤務はありません。)
お問い合わせは文学部教務課(深草・大宮)まで。