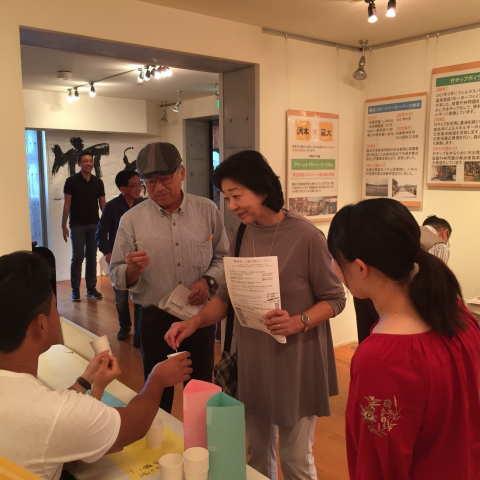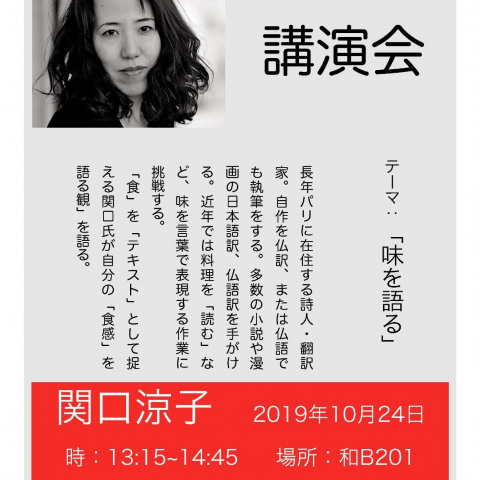京都コングレス・ユースフォーラムへの道のり4【犯罪学研究センター】
2020年4月に開催が予定されていた「京都コングレス(第14回国際犯罪防止刑事司法会議)」が新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受けて直前で開催延期となり、2021年3月7日~12日の新日程で開催されることになりました。同様に、「京都コングレス・ユースフォーラム」も、2021年2月27日・28日に開催されることとなりました。
犯罪学研究センターでは、このユースフォーラムへの龍谷大学チームの参加に向けて、「京都コングレス・ユースフォーラムへの道のり」と題し、参加学生の活動の様子をシリーズで紹介しています。
2020年10月14日、京都コングレス・ユースフォーラムに参加する学生たちと石塚伸一教授(本学法学部、犯罪学研究センター長)が集い、今後の活動について話し合いの場が持たれました。
石塚教授は英語によるディスカッションの練習の一環として、英語討論会を提案。実際にユースフォーラムで話し合われる個別テーマの1つである「青少年犯罪の予防・罪を犯した青少年の社会復帰における若者の役割」をとりあげ、まずは「犯罪を犯した少年を厳罰に処するべき」というチーム、「社会復帰の為の健全育成をするべき」というチームに分かれ、それぞれの立場についてのプレゼンを課題として提示しました。
学生たちは各々のグループに分かれて、次回の英語討論会に向けて準備をする方向で、この日の話し合いを終えました。


そして10月23日(金)、「青少年犯罪の予防・罪を犯した青少年の社会復帰における若者の役割」をテーマに、オンライン上で英語討論会が開催されました。学生たちは各々準備してきた意見を英語にて報告しました。また、本討論会には浜井浩一教授(本学法学部・犯罪学研究センター国際部門長)と古川原明子准教授(本学法学部)も参加しました。今回は青少年の厳罰に対する賛否それぞれの立場からの報告が主になりました。
「犯罪を犯した少年を厳罰に処するべき」派の意見(日本語要旨):
・犯罪被害者の視点に立つと、“少年”であるという理由だけで刑が軽くなったり、保護処分となったりするのは納得がいかないのではないか。
・日本では、2022年から民法の改正によって成人年齢が18歳となる。選挙権も18歳に引き下げられた。少年法によって保護されるべき年齢も他の法律とあわせるのが妥当ではないか。
・ちょっとした非行ならまだしも、凶悪犯罪については公開の場で審理することで事件の全容を解明をし、問題意識を社会全体で共有することが必要なのではないか。
「社会復帰の為の健全育成をするべき」派の意見(日本語要旨):
・厳罰化をしたところで、少年犯罪の根本的な解決にはならないのではないか。
・少年犯罪の原因自体が取り除かれなければ、犯罪とは別の形で社会に傷痕を残すと考える。(例:ひきこもり問題等)
・少年犯罪を単なる処罰感情のみで刑罰を定めることは野蛮であり、厳罰化することで法益がどの程度得られるかを考えて判断すべきだと考える。
・社会復帰のために、保護観察や仮釈放、教育といった方法がある。
その後のディベートでは、厳罰による成人への影響と少年への影響に関する内容が中心となりました。中には「成人と違い、少年たちは若く柔軟性があるので、厳罰ではなく、教育によって罪の認識と性格の可塑的変化が可能になるのではないか」という意見がありました。まとめとして石塚教授から「今回のディベートは非常に有意義なものだった。少年にとっては罰すること、刑罰による威嚇は重要ではない」と総括。討論を終えた後、浜井教授から「自分の意見の説得力を上げるためにも、事例を用いて説明することが望ましい。次回は、少年犯罪について、特定の問題に焦点を絞ることで、より具体的な討論が出来るのではないか」という意見と、次回の討論会に向けてのアドバイスがありました。
学生達は様々な意見やアドバイスを受け、次回の討論会では、現在の法制度やその問題点を踏まえた具体的な意見を交換することになりました。