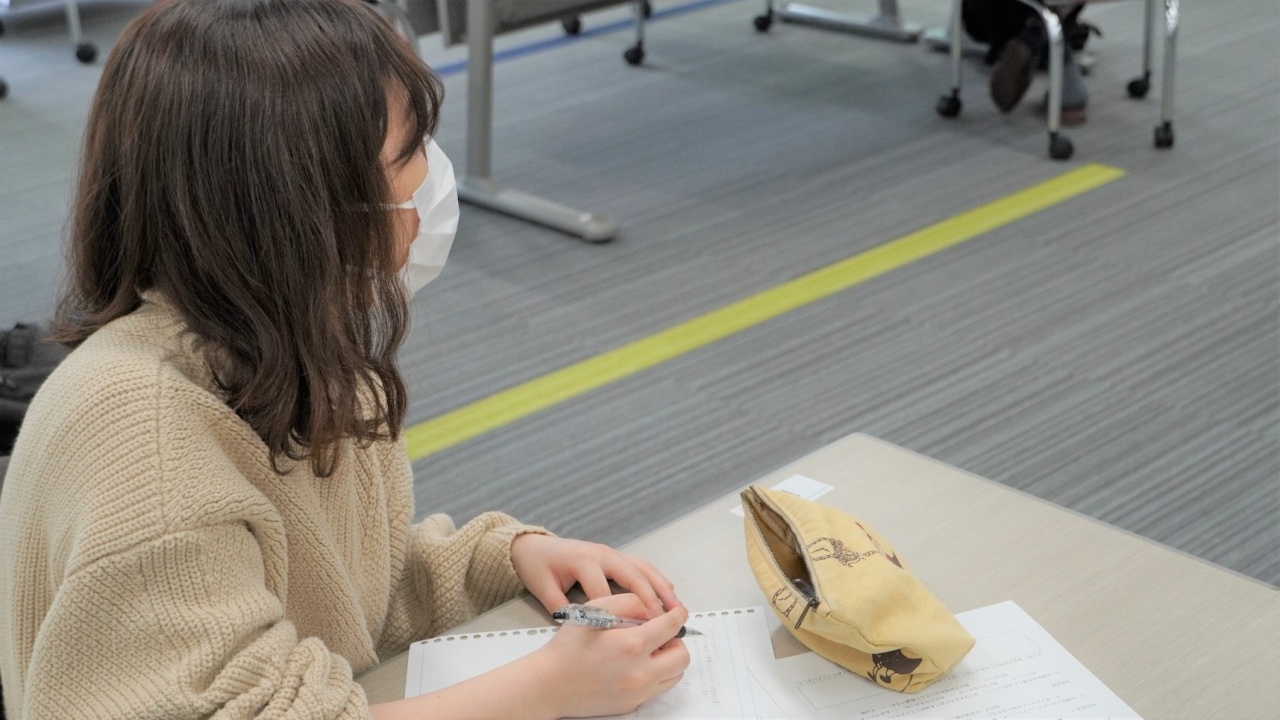【LORC共催企画】関係人口の次のステージを描く連続企画「おもろいの学校」第4回目ワークショップを開催します

洲本市の域学連携は8年目。今年は「かつて淡路島洲本市で熱い時間を過ごした皆様と、もう一度つながろう!」をテーマに、以下の企画を実施します。
洲本とすこし疎遠になってる人も、いま何してるか気になる人も、皆さん是非参加してほしいです。スタッフ一同、お待ちしています!
==================
関係人口の次のステージを描く連続企画
「おもろいの学校」第4回を開催します
==================
○詳しくはコチラ
https://bankalanka.com/
https://www.facebook.com/bankalanka.sumoto/
多くの関係人口と地域づくりに取り組んできた淡路島洲本市を舞台に、多彩なゲストと関係人口の次のステージを描く全4回の連続企画「おもろいの学校」。
これまで3回ワークショップ形式で開催し、「おもろいとはなにか」「おもろい企画をつくる発想法」「おもろさを持続するヒント」について学びました。その結果、3つのリードプロジェクトが「おもろく」仕上がり、洲本市で実行することになりました。
最終回となる第4回では、完成した3つのプロジェクトを発表するとともに、地方の「おもろさ」をどのように伝え拡げるかについて考えるワークショップを開催します。
辞書に載っている「面白い」ではなく、私たちなりの「おもろい」をつくりだす方法を一緒に考えませんか?
○こんな人に参加してほしい
・これからのローカルビジネス、まちづくりに関心がある
・自身の取り組みやチームに「おもろさ」を取り入れるヒントが欲しい
・自分たちの町に「関係人口」を生み出す秘訣を知りたい
○キーワード
#関係人口 #地域づくり #ローカルビジネス #おもろさ #企画 #SDGs
=================
おもろいの学校@洲本 #04
「"おもろさ"を伝え拡げるために」
日時:1月31日 (日) 16:00-19:00
会場:オンライン(zoom)にて開催します。前日、前々日に参加申し込み者にURLをご案内します。
申込:以下のエントリーフォームに必要事項をご記入の上、お申し込みください。(1/28締切)
https://forms.gle/hVsyiQytsKLpBbam8
料金:無料
定員:50名
内容:
・講演「"おもろさ"を伝え拡げるために」 田中 輝美 氏
・セッション「内と外をつなぐ情報発信」 田中 輝美 氏 × 龍谷大学 × 洲本市役所
・話題提供「ローカルプロジェクトの発表会」
PJ①:洲本市若手職員とともに「おもろい洲本」のまちづくりに繋がるプロジェクトを育てる【みんなで育てる"おもろいの種"プロジェクト】
PJ②:洲本市で学生のための拠点整備を行い学生の活動を支援する【洲本市拠点整備】
PJ③:土地への新たな回路を開く観光事業をつくる【「名もなき観光」事業】
・意見交換会、フィードバック
・ゲスト:田中 輝美 氏
http://www.tanakaterumi.com/
ローカルジャーナリスト。島根県浜田市出身。大阪大学文学部卒業後、山陰中央新報社に入社し、ふるさとで働く喜びに目覚める。2014年秋、同社を退職して独立、変わらず島根を拠点に活動している。著書に『関係人口をつくる』(木楽舎)、共著に『みんなでつくる中国山地』(中国山地編集舎)など。2020年、大阪大学大学院人間科学研究科で関係人口をテーマに研究し、博士(人間科学)を取得。第11回ロハスデザイン大賞2016受賞。
○主催:洲本市域学連携推進協議会(洲本市役所企画課内)
○共催:龍谷大学地域公共人材・政策開発リサーチセンター(LORC)
○お問い合わせsumoto.ryukoku2020@gmail.com(担当:龍谷大学・櫻井、洲本市・高橋)