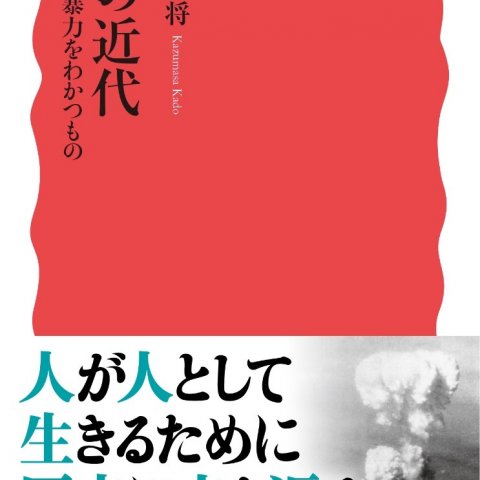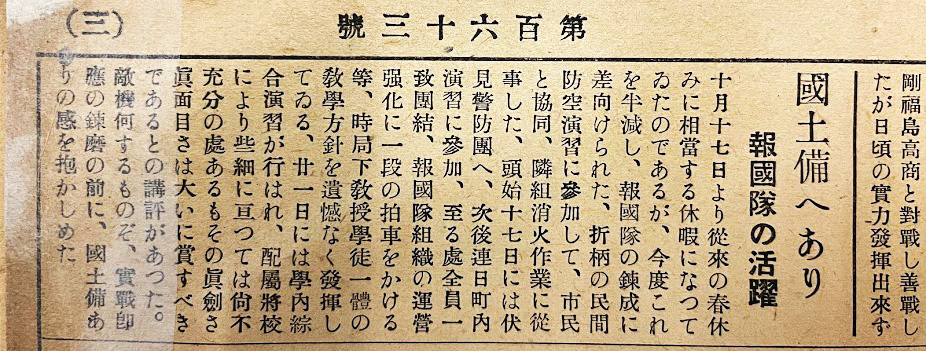2023年度 アカデミック・スカラシップ奨学生(在学採用型)授与式を実施しました。【文学部】
本学では、学部2~4年次生の学業成績・人物が特に優秀な学生を対象に「アカデミック・スカラシップ奨学生(在学採用型)」の制度を設けています。
2023年度に採用された3・4年次生を対象とする表彰状授与式が、大宮学舎本館にて2023年7月7日(金)に実施されました。
大宮学舎では文学部長の玉木興慈先生から、賞状の授与と祝辞がありました。
賞状授与後の玉木興慈学部長祝辞
『アカデミック・スカラシップ奨学生に採用され、奨学金を授与されることになったみなさん、おめでとうございます。
みなさんが本奨学生に採用されたのは、学業成績はもちろん、人物としても特に優秀であると認められたからです。これまで努力を怠らずに学びを深めてきたからこその賜物です。今後の更なる活躍に期待しています。
そして、これからも多くの仲間たちによい刺激を与え続けてください。
名称は違いましたが、私が学生時代に、いただいた奨学金があります。その時に、担当の先生がこのようなことをおっしゃいました。
お浄土に往生したら、先立ったいろんな方に会える。親であったり、祖父母であったり、先生であったり、時には、自分よりも若い年齢で亡くなった方など、多くの方のお顔を思い浮かべることができます。その中のお一人が、親鸞聖人です。いずれお浄土に往生させていただいて、親鸞聖人に会うことができた時に、顔向けできないような奨学金の使い方だけはしないでほしい。あの時の奨学金は、こんな風に使わせていただいた、と真正面向いて、報告できるような使い方をしてほしい。
そんな言葉でした。皆さんにも、同じような思いをお伝えします。
もう一つ。文学部の皆さんは、1回生の時、月曜日2講時目にあった講義を覚えていますか?成績優秀な皆さんは、直ぐに思い出せるかと思います。そうです、「仏教の思想A・B」ですね。釈尊の生涯や言葉、親鸞聖人の生涯や言葉を学び、建学の精神について学ぶ講義でしたね。その講義の中で、因果・縁起について学んだと思います。
因果とは、善い結果が出ている時には、善い原因が必ずあるということです。これを善因善果といいます。逆に、悪い結果が出てしまった時には、悪い原因がやはり必ずあるということです。これを悪因悪(苦)果といいます。原因と結果の強い結びつきを因果と呼びますが、因と果の間には、縁と呼ばれる条件のような事もあります。善い原因があれば必ず良い結果につながるかと言えばそうではありません。原因と結果の間に、無数の縁(条件)が重なって、そこに始めて、善因と善果がつながります。
ここからが大切なことです。今回の皆さんのアカデミック・スカラシップ奨学生採用は、間違いなく善果です。そして、皆さんのたゆまぬ努力という善因があったことも間違いの無い事実かと思います。自身の努力を誇りに思い、自身をほめる気持ちもあって良いと思います。でも、自分を頑張らせてくれた様々な縁に感謝する気持ちを忘れないでほしいと思います。
逆に、悪い結果が出た時はどうでしょうか?悪い原因があったハズですが、私たちは、得てして、自身の悪因には目を伏せ、因果の間にある縁に責任をなすりつけることは無いでしょうか。誰かに責任転嫁するようなことです。それでは自立した人間とは言いがたいと思います。自身の足りなかった点、至らなかったことを、厳しく見つめることが自立した人間に求められていると思います。
善い結果の時ほど縁に感謝できる人間、悪い結果の時には自身の悪因を厳しく見つめられる人間。これが、建学の精神に照らして考えられる一つの理想の人間像では無いでしょうか。
自身の欠点や弱点は見たくないものです。また人にも知られたくないものです。けれども、しっかりと目を凝らして見るようにしてください。これは、厳しく辛い作業と思います。でも、この作業を経ることによって、本当の力が備わると思います。より高次な飛躍が可能になると思います。
厳しい作業は、一気に進めることはできません。自分だけで進めることも難しいと思います。日々の生活の中で、地道に継続する、ここに大きな可能性が開かれると思います。龍谷大学文学部は最大限の応援をしたいと思います。
奨学生のみなさんがさらに学びを広め深め、その成果を実感できるよう研鑽を重ねつつ、光輝ある学生生活を送られることを念じます。』
奨学生には給付対象者となったことを励みに、より一層飛躍することを期待しています。